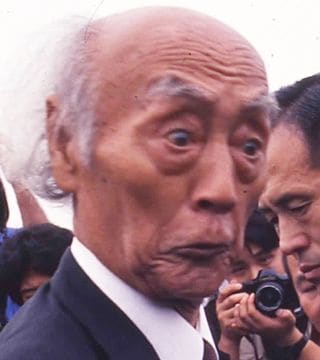昭和に始まったかなまら祭
金山神社という名前の神社は日本の各地に存在し、昔から鉱山や鍛冶屋など金属に縁のある人に信仰されてきた。この川崎の金山神社も鉱山や鍛冶の神である金山比古神(かなやまひこのかみ)と金山比売神(かなやまひめのかみ)を祀っている。
 大きなアレを抱えた天狗も登場(写真:橋本 昇)
大きなアレを抱えた天狗も登場(写真:橋本 昇)
同時に、この神様は性的な象徴ともされ、この神社も江戸時代には夫婦和合、子宝繫栄などの性的な信仰を集めていたという。しかし、昭和の高度成長期になると、鉄の神様としての側面のみが残り、性的な信仰は忘れ去られていった。
「かなまら祭」が行われるようになったのは1969年からというから、この祭自体は古くからの祭ではない。川崎ではその昔に「地べた祭」という花見の時期に地べたからエネルギーをもらって下半身の病を治そうという祭があったそうで、その「地べた祭」の復活と寂れた神社の復興を目的として考え出されたという。「かなやま」と「かなまら」の語感も似ている。
この祭が一気にブレイクしたのは10年ほど前で、きっかけは外国人観光客のSNSへの投稿だった。
 男性のシンボルが描かれた紙製サンバイザーをかぶる夫婦(写真:橋本 昇)
男性のシンボルが描かれた紙製サンバイザーをかぶる夫婦(写真:橋本 昇)
祭の花は神輿だが、ここではとんでもない神輿が登場した。古木で作った太い男根が鎮座している。それを氏子たちが担いで観光客でいっぱいの通りを練り歩く。
 通りを練り歩く2台の“男根神輿”(写真:橋本 昇)
通りを練り歩く2台の“男根神輿”(写真:橋本 昇)
続いて登場した何とも奇妙な神輿に観光客の目は点になった。巨大なピンク色の男根が天に向かってそそり立っている。