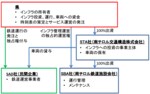乗客減のローカル線、魅力はこう磨く!廃線から劇的復活「ホームで乾杯」「両側乗降」イタリアの鉄道に学ぶ先行投資
【世界基準で考える公共交通】「輸送密度1千人未満」の鉄路に未来はあるか?(中編)
柴山 多佳児
ウィーン工科大学交通研究所上席研究員
2024.6.27(木)
ここからは、JBpress Premium 限定です。
カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら
連載の次の記事
ボロボロのローカル線、廃線後に130億円投資で復活…「人口減を回避」「観光にプラス」イタリアの“お手本”に学ぶ