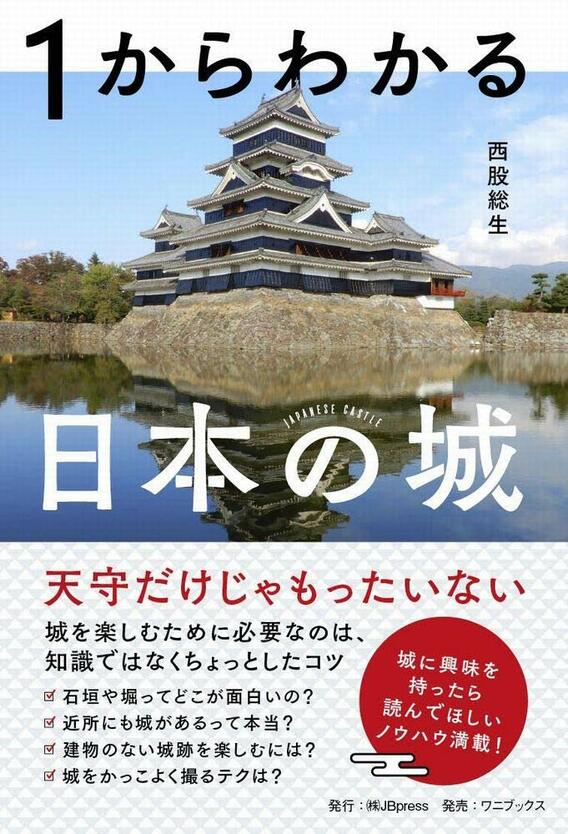津軽鉄道の「走れメロス号」撮影/西股 総生(以下同)
津軽鉄道の「走れメロス号」撮影/西股 総生(以下同)
(歴史ライター:西股 総生)
「滅び」と「裏切り」
「メロスは激怒した。必ず、かの邪智暴虐の王を除かねばならぬと決意した。メロスには政治がわからぬ。メロスは、村の牧人である。」
こんなふうに始まる太宰治の短編小説『走れメロス』は、日本人なら知らぬ人とてない名作だ。あなたも中学か高校の時分に、たぶん国語の教科書で読んだ経験がおありだろう。
 太宰治
太宰治
早くに両親を亡くした牧童のメロスは、妹の婚礼に必要な品々を揃えるために、シラクスの街にやってきたが、街の様子がおかしい。聞けば新王のディオニスは暴君で、猜疑心から家族や家臣・市民を次々捕らえては殺すため、皆戦々恐々としているとのこと。
「聞いて、メロスは激怒した」暴君許すまじ、と懐に短剣を忍ばせて王城に押し入ったが、たちまち捕らえられ王の面前に引き出される。
 右から角川文庫、新潮文庫、集英社文庫。『走れメロス』は他にも岩波文庫や文春文庫でも読むことができる
右から角川文庫、新潮文庫、集英社文庫。『走れメロス』は他にも岩波文庫や文春文庫でも読むことができる
メロスは王に訴えた。自分が処刑されるのは仕方がないが、婚礼を待っている妹が不憫だから、三日の猶予がほしい。その間に村に帰って婚礼を済ませたら、自分は再び王城に駆け戻って刑に服する、替わりにこの街に住んでいる親友のセリヌンティウスを人質とするから、自分が刻限までに戻らなかったら、セリヌンティウスを処刑してくれ、と。メロスの話を面白がった王は、セリヌンティウスを牢に入れてメロスを放す。
大急ぎで村に帰ったメロスは、婚礼を済ませると街に駆け戻ろうとする。濁流を泳ぎ山賊を斬り伏せ、必死に走るものの、気力体力が尽きて倒れ込んでしまう。しかし、泉の水で喉を潤すと息を吹き返し、再び走りに走って、間一髪で刻限の日没に間に合う。
見守っていた群衆の歓呼に包まれながら、メロスはセリヌンティウスと再会を喜ぶ。王もついに自分の非を悟って二人を許し、三人は抱き合ってハッピーエンドを迎える、という物語である。
ギリシャの古典やシラーの詩を題材として書かれたこの作品を、多くの人は正義と友情の物語として読んだことだろう。いや、教科書ではそのように読ませているし、各種の作品解説でもそのように解釈されている。
 太宰の生家である金木の「斜陽館」
太宰の生家である金木の「斜陽館」
けれども筆者は、この作品を正義と友情の物語として読むことに、疑問を持つ。なぜなら、太宰文学全体を通底するメインテーマが、「滅び」と「裏切り」であるからだ。
津軽の大地主の六男坊として生まれた太宰治(本名・津島修治)は、東京帝大在学中に左翼運動に参加するも転向し、二度も女性と心中未遂事件を起こした挙げ句、酒や薬物に溺れた。
けれども文学への志を捨て切れず、療養ののち師と仰いだ井伏鱒二の斡旋で、甲府の石原美知子と結婚。生活を立て直して多くの作品を書いたものの、昭和23(1948)年6月13日、愛人の山崎富栄とともに玉川上水に身を投げて、39年の生涯を閉じた。なお、太宰の命日は二人の遺体が発見された6月19日とされ、「桜桃忌」と呼ばれている。
 甲府市の太宰新婚居宅跡
甲府市の太宰新婚居宅跡
太宰が『走れメロス』を発表したのは昭和15(1940)年、美知子夫人との新居を甲府から三鷹へと移した直後である。この時期の太宰の作品は、たしかに明るい。人間の性(さが)のようなものを、闊達に、ユーモラスに描いていることが多い。ただし、では「滅びと裏切り」というテーマから離れているのか、というと、決してそうではないのだ。
たとえば、『走れメロス』と同時期の短編で、やはり一気呵成の佳作である『駆け込み訴え』は、ピラト総督のもとに駆け込んだユダが、キリストへの恨み辛みをとうとうと述べる話である。また、甲府時代に野良犬を拾ったエピソードを描く『畜犬談』は、ユーモラスな小品である。けれども、薬殺を企ててなぜか死ななかった犬に、心中未遂からおめおめ生き残った自分を投影していて、ユーモアが自虐的である。
 甲府の新婚時代に太宰が通った「喜久乃湯」。今も地元の人々に親しまれている(写真はたまたま休業日)
甲府の新婚時代に太宰が通った「喜久乃湯」。今も地元の人々に親しまれている(写真はたまたま休業日)
『走れメロス』を単体で読むと、たしかに正義と友情の物語のように思える。しかし、作家の生涯を踏まえた上で、他の作品群と対比して読むならば、まったく別の解釈も成り立つのではないだろうか。(つづく)
*6月8日掲載の拙稿「意外にも太宰治ゆかりの名城・甲府城」もご参照下さい。