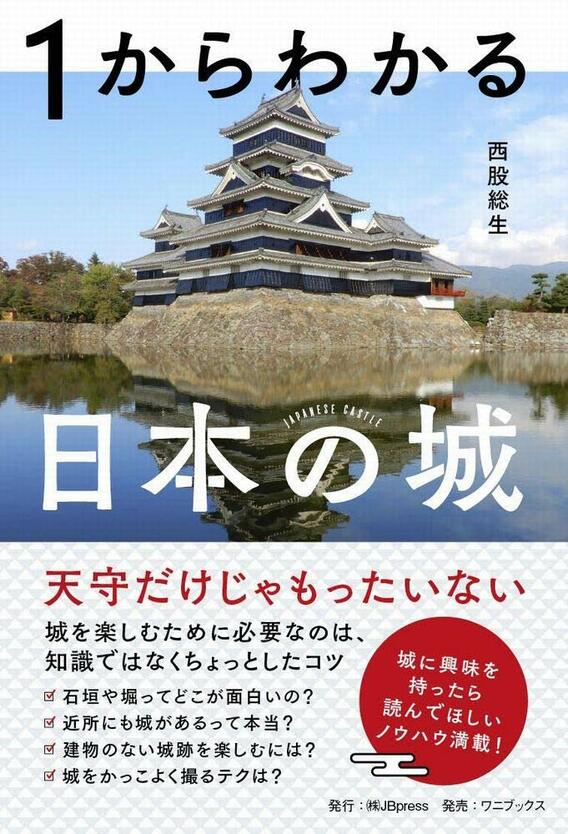江戸城の天守台 撮影/西股 総生(以下同)
江戸城の天守台 撮影/西股 総生(以下同)
(歴史ライター:西股 総生)
徳川家の家老こそが老中
本サイト3月14日掲載の「江戸幕府の老中はなぜ譜代大名が独占するのか?近代的な政府や会社組織とは全く違う「幕府」の基本原理」では、江戸幕府の基本的な原理を説明した。
すなわち、われわれが「江戸幕府」と呼んでいる権力は、もともとは徳川家という「家」であるから、徳川家に代々仕えてきた譜代大名が「番頭さん」として徳川家の業務を仕切る。この「番頭さん」、言い換えるなら徳川家の家老こそが老中なのである。
そのように説明してくると、「門閥譜代」などという言葉を思い浮かべる人もあるだろう。特定の家の者たちが、コップの中の嵐のような抗争を繰り返しながら、権力をたらい回ししているイメージだ。
 浜松城。家康のかつての本拠であったこの城には有望な譜代大名が入れ替わり立ち替わり封じられて多くの老中を輩出して「出世城」の異名を取った
浜松城。家康のかつての本拠であったこの城には有望な譜代大名が入れ替わり立ち替わり封じられて多くの老中を輩出して「出世城」の異名を取った
しかし、実際には幕府の権力構造は、もっと柔軟であった。まず、老中を輩出する譜代大名家が10家や20家ではない。時期によって多少の変動はあるものの、全国でおおよそ260〜270家ほどあった大名家のうち、ほぼ半数くらいは譜代大名である。
そのうちで老中に登用されるのは2万5千石以上の大名だが、それだって何十家とある。対して老中の定員は3〜5名であったから、かなりな競争を勝ち抜かなければたどり着けない。相応の政策立案能力なり、政界遊泳術なりを身につけなければ無理なのだ。
 福山城に建つ阿部正弘(1819-57)像。正弘は奏者番や寺社奉行をへて老中となり幕末の難局に対処した
福山城に建つ阿部正弘(1819-57)像。正弘は奏者番や寺社奉行をへて老中となり幕末の難局に対処した
また、江戸時代には家を絶やさないために、男子に恵まれない家では養子を迎えることが広く行われていた。一般に武家の男子は保守的な価値観を植え付けられがちであるが、養子に出されるのは次男以下だから、行動や発想の柔軟な者も多い。大名家の先々代・先代が頭の固いボンクラでも、優秀な養子が来れば出世の道も開けよう。
さらに、5代将軍綱吉のときには「側用人」というポストが新設された。幕府の業務と官僚機構がふくらんでゆくなかで、実務を取り仕切る老中らを牽制しながら、将軍自らが政策に携わることを可能とするシステムである。
側用人は、将軍の個人秘書みたいな立場だから、一定石高以上の譜代大名といった縛りはなく、将軍が気に入りさえすれば身分の低い者でも取り立てることができた。側用人の元祖である柳沢吉保は、綱吉が館林藩主だったときの小姓であったし、6代家宣・7代家継に仕えた間部詮房(まなべあきふさ)は猿楽師、田沼意次は紀州藩足軽の家に生まれた者である。
 松坂城下に残る足軽長屋。田沼意次もこのような粗末な長屋で生まれ育ったのだろう
松坂城下に残る足軽長屋。田沼意次もこのような粗末な長屋で生まれ育ったのだろう
由緒ある譜代大名の老中は当然、成上がり者の側用人を快く思わない。そこで将軍は、側用人の知行を加増して大名に取り立て、老中に対抗できる立場を与えた。柳沢吉保は加増を重ねて15万石を得たが、これは譜代大名としてはトップクラスの石高になるので、大老に準ずる立場となった。田沼意次も5万7千石を得て側用人と老中を兼任し、政策を主導している。
 甲府城。柳沢吉保は加増が重ねられて甲府15万石を領するに至った
甲府城。柳沢吉保は加増が重ねられて甲府15万石を領するに至った
ところで、江戸時代を通観してみると、経済がインフレ傾向にある時期とデフレ傾向の時期とが、数十年スパンで交替していることがわかる。いつの世も、右肩上がりの経済成長が永遠に続いたりはしないのだ。
そこでインフレ期には、幕府は公共事業を積極的に行って重商主義的政策を進めていった。柳沢吉保や田沼意次のように出身身分の低い者は、「経済」を肌感覚で知っていたし発想も柔軟なので、こうした局面では大いに才能を発揮できた。
一方のデフレ期には、幕府は緊縮財政をしいて農本主義政策に回帰するから、松平定信のように保守指向が強く、藩主として領内統治に実績をもつ者が政策を主導することになった。
 白河小峰城。田安家に生まれた定信は白河藩松平家の養子となり、のち老中となって寛政の改革を断行した
白河小峰城。田安家に生まれた定信は白河藩松平家の養子となり、のち老中となって寛政の改革を断行した
以上のように見てくると、人材登用システムが柔軟であったからこそ、江戸幕府は270年近くも政権を維持できたことがわかる。少数の門閥譜代だけでたらい回しをやっていたら、社会や経済の変化には対応できないのである。
などという背景を理解していると、大河ドラマ『べらぼう』で描かれる幕府内部の権力闘争も、より深く楽しめるだろう。