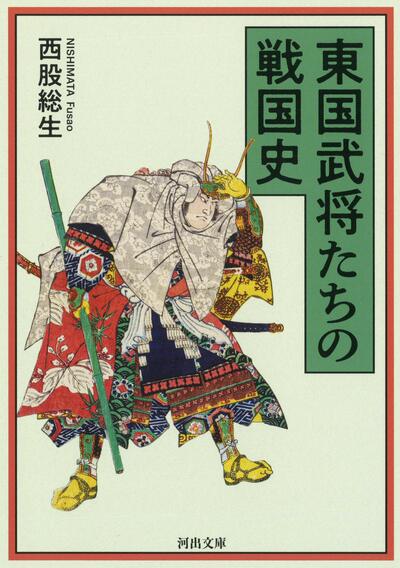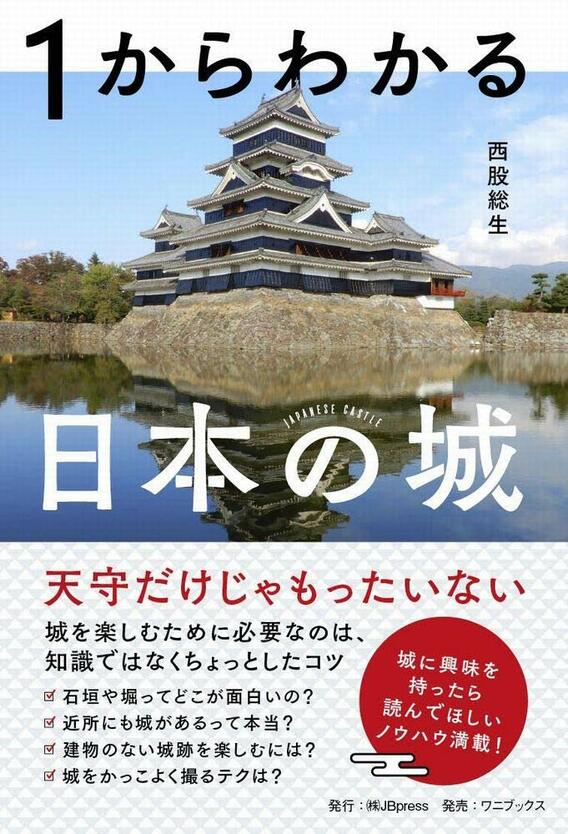撮影/西股 総生(以下同)
撮影/西股 総生(以下同)
(歴史ライター:西股 総生)
「江」は川や入江、「戸」は出入り口や船着き場を指す
もともと「江戸」の「江」は川や入江を、「戸」は出入り口や船着き場を指す言葉といわれている。だとしたら、「江戸」とは河口だとか入江の船着き場を意味する地名、と考えることができそうだ。前稿「江戸城は「平山城」?それとも「平城」?江戸城の占地から見えてくる都市・江戸の成り立ち」で確認した江戸城の占地を、この地名の成り立ちに重ね合わせてみよう。
 現在の江戸城天守台から見た本丸。道灌の江戸城もこの場所にあった
現在の江戸城天守台から見た本丸。道灌の江戸城もこの場所にあった
江戸湾という、懐の深い大きな湾の一番奥に、大小の河川が流れ込んでいる場所が江戸だった。この「江戸」という地名が史料で確認できるのは鎌倉時代に入ってからだが、地名そのものはもう少し前、平安時代の終わり頃には存在していたらしい。
関東に下った桓武平氏の末裔である秩父氏流という一族が、荒川に沿って勢力を広げてゆき、下流の平野部にも住み着くようになる。武蔵北部の畠山氏や河越氏がそれで、さらに南下して江戸氏・葛西氏・豊島氏といった一族が成立していった。やがて源頼朝が挙兵すると、彼らもほどなく帰参して鎌倉幕府の御家人になる。
 埼玉県嵐山町の菅谷城址に立つ畠山重忠像(実際には城と重忠は関係なさそうだが)
埼玉県嵐山町の菅谷城址に立つ畠山重忠像(実際には城と重忠は関係なさそうだが)
その江戸氏が本拠を置いていたのが、江戸城のあたりとされている。ただし、当時の武士の本拠のあり方からして、屋敷があったのは本丸(つまり台地の上)ではなく、現在の二ノ丸のあたりであろう。
ところで、近代以前における内陸部での物流手段というと、馬を思い浮かべる人が多いだろう。けれども、実際は馬と同じくらい、あるいは馬以上に重要だったのが河川交通、つまり川船である。川船は、関東だと冬場などの渇水期には使えないという欠点もあるが、馬よりもはるかに大量の物資を低コストで運ぶことができる。
なぜ、こんな話をしたかというと「江戸」である。湾の奥に川が流れ込んでいて船着き場のある場所では、海上輸送から川船や馬への積み換えが行われる。そんな場所には当然、市が立つし、船乗りが休むための施設もできて、人が集まる。江戸氏が居を構えた頃の江戸は、そんな集落であったろう。
 江戸城西ノ丸下(皇居外苑)から見た大手町のビル街。かつてこのあたりは砂浜や浅瀬だった
江戸城西ノ丸下(皇居外苑)から見た大手町のビル街。かつてこのあたりは砂浜や浅瀬だった
とはいえ、都市と呼べるほどの賑わいではない。何せ、平安時代の日本で都市と呼べるのは、京都・奈良と大宰府くらいのものだったからだ。やがて、頼朝が幕府を開いたことで鎌倉が都市になり、少しずつ地方地方にも小さな町場ができてゆく。武士が時代の主役となって京都一強の中央集権体制が崩れ、それまで中央に吸い上げられていた富が横方向にも動くようになってきたことに加え、貨幣経済が浸透してきたからである。
 長野県上田市別所にある安楽寺八角三重塔。同寺は鎌倉時代に執権北条氏の庇護で栄えた
長野県上田市別所にある安楽寺八角三重塔。同寺は鎌倉時代に執権北条氏の庇護で栄えた
さらに南北朝時代になると、万単位の軍勢が日本列島を東へ西へと転げ回った結果、物流が活性化した。また、室町幕府が各国に置いた守護が「守護大名」となって地域権力化していったことで、守護所の周囲に人が集まって次第に地方都市が形成されていった。
江戸城が築かれたのは、そんなふうに社会が変化しつつある長禄元年(1457)のこと。扇谷上杉家の家宰という職にあった太田道真・道灌という親子が、この場所に目を付けたのである。家宰というのは、筆頭家老みたいな立場だ。
 日暮里駅前に立つ太田道灌像
日暮里駅前に立つ太田道灌像
室町時代の関東を支配していた権力は、この頃には公方(くぼう)と管領とに分裂し、公方側は古河を本拠として関東の東半分を、管領側は西半分を勢力圏としていた。その管領家の分家が、道真・道灌が仕えた扇谷上杉家である。
公方勢力と対峙する管領軍は、北武蔵の五十子(いかっこ)というところに本営を置いていたが、公方勢力が“戦線”の南側を突破しないための防衛拠点が必要になった。そこで、分家の扇谷家が“戦線”南側の防衛担当となって、江戸城が築かれることになったわけだ。(つづく)
 江戸城西ノ丸にある道灌堀。実際には戦国時代の遺構ではないが、昔風の土造りの堀としてそう呼ばれるようになったものか
江戸城西ノ丸にある道灌堀。実際には戦国時代の遺構ではないが、昔風の土造りの堀としてそう呼ばれるようになったものか
[参考図書]太田道灌の戦略と戦術に興味のある方は『東国武将たちの戦国史』(河出文庫)をご一読下さい。