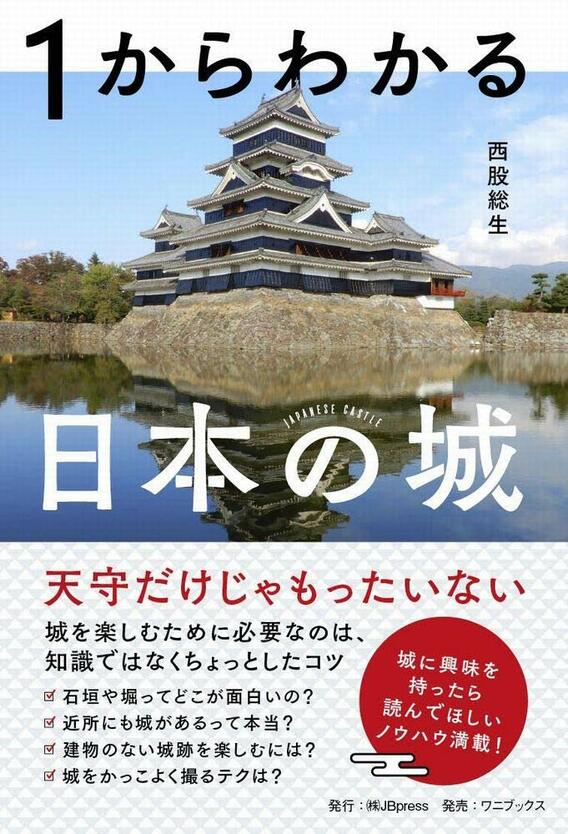鶴岡八幡宮 写真/アフロ
鶴岡八幡宮 写真/アフロ
(城郭・戦国史研究家:西股 総生)
大江広元や三善康信は「正社員」
前回に引き続き、源仲章のお話です。いえ、別に生田斗真さんのファンというわけではなく、仲章のような人物の出現は、この時期の鎌倉幕府のあり方を象徴している、と考えられるからです。
ポイントは、大江広元や三善康信が幕府の「正社員」なのに対し、仲章は院からの「出向社員」という、前回持ち出したたとえです。鎌倉幕府のあり方を、おさらいしてみましょう。
もともと頼朝の挙兵は、追い詰められた流人によるイチかバチかの叛乱でした。ところが、三浦一族や上総介広常・千葉常胤といった有力武士団が合流したことにより、叛乱は坂東独立運動の性格を帯びるようになりました。
そして、頼朝が立ち上げた革命政府のような鎌倉には、広元や康信のような京下りの文官もやってきました。彼らは、何らかの事情で都に居づらくなったり、あるいは役人稼業に見切りをつけて来た人たち、言い換えるなら、都での貴族としての生き方を捨てて革命政府に身を投じた人たちです。実際、広元も康信も鎌倉に骨を埋めることになりました。
 大江広元墓所
大江広元墓所
こののち鎌倉は、木曽義仲・平氏・奥州藤原氏といった強敵を次々と倒し、勢力を伸ばします。つまり、所領や権益を次々と手に入れていったわけです。「敵から奪えるものは、奪えるだけ奪え」というノリだったに違いありません。
ところが、強敵をひととおり倒して「戦争の季節」が終わると、次は「政治の季節」に入ります。もはや「奪えるだけ奪え」というわけにはいきません。鎌倉には、法や道理にのっとった権力であることが求められます。
当然、京の朝廷とも折り合ってゆかなくてはなりません。悲劇的結末におわった大姫入内計画も、「朝廷とどう折り合うか」というテーマに発した問題だったことがわかります。そして、この課題の決着を見ることなく、頼朝は世を去ってしまいました。
頼朝の死後、幕府を支えてきた宿老達は権力闘争を繰りひろげ、北条義時が最終的な勝者として残りました。しかし、頼朝が残した「朝廷とどう折り合うか」という課題は、根本的には何も解決されていませんでした。
一方で、権力機構として成長した鎌倉幕府の事務量は、増える一方です。京から多くの文官たちを招かなくては消化しきれません。とともに、鎌倉の人口が増えてゆけば、都市としての経済規模も大きくなります。頼家や実朝が文化事業に力を入れた事とも相まって、鎌倉の文化度は上がってゆきます。陳和卿のような怪しげな外国人が引き寄せられてくるのも、当然だったのです。
 陳は焼損した東大寺大仏の鋳造と大仏殿の再建に尽力した。写真/アフロ
陳は焼損した東大寺大仏の鋳造と大仏殿の再建に尽力した。写真/アフロ
こうした状況下で新しくやって来る文官たちは、都での貴族としての生き方を捨てて鎌倉に骨を埋めるような覚悟は、もはや持っていなかったでしょう。彼らの代表こそが、院からの「出向社員」である仲章なのです。
和田義盛という強敵を倒して権力を手中におさめたとき、義時の前に広がっていたのは、頼朝時代とはすっかり様変わりした大所帯の鎌倉でした。あまつさえ実朝からは、子作りの放棄という形で後継者問題を突きつけられています。「朝廷とどう折り合ってゆくか」という宿題を含めて、義時は、曲がり角に差しかかった鎌倉の難しい舵取りを迫られていたのです。
※実朝暗殺の背後関係についての筆者の推理については、拙著『鎌倉草創-東国武士たちの革命戦争』(ワンパブリッシング)をご参照下さい! Kindle版も好評です。