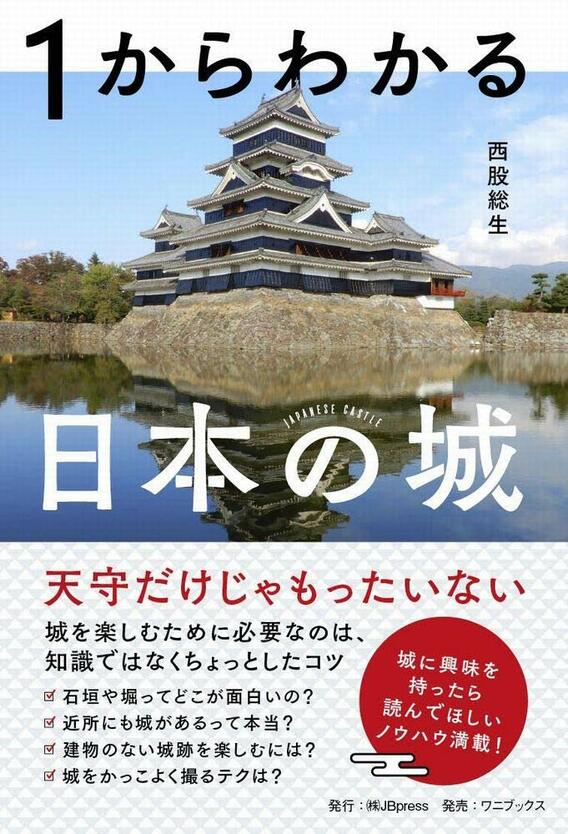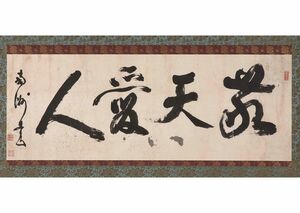写真/西股 総生(以下同)
写真/西股 総生(以下同)
(歴史ライター:西股 総生)
甲府の地をとりわけ重視した秀吉
「甲府は盆地である。四辺、皆、山である」 甲府で新婚生活をスタートさせた太宰治は、同地を舞台にした短編小説『新樹の言葉』を、こんな一文で始めている。
「シルクハットを倒(さか)さまにして、その帽子の底に、小さい小さい旗を立てた、それが甲府だと思えば、間違いない」と。であるなら甲府城は、その小さい旗の掲揚台にたとえられようか。
 天守台から西に甲斐の山々を望む。遠くに白根三山が見える
天守台から西に甲斐の山々を望む。遠くに白根三山が見える
何といっても、この城は甲府の駅に近い。中央本線のホームから、高い石垣と、その上に復元された稲荷櫓を、見上げることができる。というか、甲府の駅そのものが本来は城内で、中央本線は城を貫通しているのである。
 中央本線と甲府駅をはさんで南側には稲荷櫓、北側には山手門が復元されている
中央本線と甲府駅をはさんで南側には稲荷櫓、北側には山手門が復元されている
天正10年(1582)年3月、織田信長は武田勝頼を滅ぼして甲斐を併呑し、家臣の河尻秀隆を入部させた。ところが、直後の6月に本能寺の変が起きて織田家の覇権は崩壊。甲斐は無政府状態となって、河尻秀隆は蜂起した武田遺臣らに殺されてしまう。こののち甲斐を領したのは徳川家康であったが、天正18年(1590)年の小田原の役によって関東に移り、甲斐は豊臣政権の支配下に置かれることとなる。
まず、秀吉の甥に当たる羽柴秀勝(秀次の弟)が入り、城の主は加藤光泰→浅野長政→幸長と目まぐるしく交替。そこで、実際の甲府築城は加藤以降と見るのが通説となっている。秀勝の在甲府は1年に満たないし、加藤・浅野時代に普請が進められて城が完成に至ったこともわかっているからだ。
 天守台の平面形はひどく歪んでいる。さぞかし前衛的な桃山デザインの天守が建っていたことであろう
天守台の平面形はひどく歪んでいる。さぞかし前衛的な桃山デザインの天守が建っていたことであろう
ただ、秀吉が甥クラスの有力武将を占領地に封じた例は他にない。どうも秀吉は、関東に対する押さえとして、甲府の地をとりわけ重視したようなのである。だとしたら、甲府城の基本設計は秀勝の時期になされた、と考えてよいのではないか。というより、それこそが秀勝に与えられた任務ではなかったか。
以上のように考えたとき、甲府城の姿は、非常なリアリティをもって立ち上がってくる。まず、この城は縄張が異常にタイトで、実戦的だ。居住性をかなぐり捨ててでも防禦力を高めよう、といわんばかりに、通路を執拗に折り曲げて、敵の侵入を頑なに拒んでいる。縄張が、ただならぬ緊張感に満ちているのだ。
 左手の内松陰門から本丸銅門(右手)までの通路は屈曲を繰り返しながら石段を登る。突破はきわめて困難だ
左手の内松陰門から本丸銅門(右手)までの通路は屈曲を繰り返しながら石段を登る。突破はきわめて困難だ
石垣の築造技法も、古態をとどめている。これは、石垣の角部分の稜線を見れば、城に詳しくない方でも理解できるだろう。さほど急ではない勾配で直線的に立ち上がり、算木積みも未完成な様子が見てとれる。全体に石のサイズも不揃いで、目地の通らないランダムな積み方をしている。天正末〜文禄年間(1590年代前半)の技法、と見て間違いない。
 数寄屋曲輪東側の石垣。古態な技法をとどめており貴重だ
数寄屋曲輪東側の石垣。古態な技法をとどめており貴重だ
にもかかわらず石垣が、高い。江戸時代に積み直された箇所や、近代以降に補修された箇所も多いが、天守台や本丸周辺には、古い技法をとどめる高石垣がそのまま残されている。この古態な技法で、この高さまで積み上げているという意味では、東日本では江戸城に次ぐ貴重な石垣といってよい。豊臣政権が甲府の地をいかに重視したか、である。
 復元された稲荷櫓を見上げる。城は徳川綱重期以降に改修され、櫓や城門は一新されたようである
復元された稲荷櫓を見上げる。城は徳川綱重期以降に改修され、櫓や城門は一新されたようである
むろん、江戸幕府も戦略の要衝として甲府を重視した。徳川綱重(4代将軍家綱の弟)、その子綱豊(のちの6代家宣)、柳沢吉保といった面々が城主を務め、柳沢家が大和郡山に転じてのちは、幕府直轄となった。こんな城を、名城といわずして何とする。
太宰は『新樹の言葉』の中に、市中で起きた火事を眺めるため甲府城の石段を登ったエピソードを書いている。また、甲府の街をこんなふうにも評している。「派手に、小さく、活気のあるまちである」「きれいに文化のしみとおっているまちである」と。
甲府城は、そんな街の真ん中に鎮座する、新緑の似合う名城である。
 富士には月見草がよく似合うように、甲府城には桜より新緑の方がよく似合う、と個人的には思う
富士には月見草がよく似合うように、甲府城には桜より新緑の方がよく似合う、と個人的には思う
[参考図書] はじめて城を歩く人、これけから本格的に城歩きをしたい人のための、城の見方の基礎が身につく本、西股総生著『1からわかる日本の城』(JBprees)好評発売中!