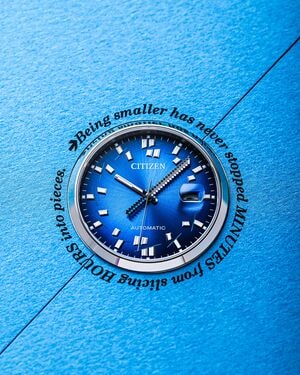(写真:siro46/Shutterstock)
(写真:siro46/Shutterstock)
「50代は老いの思春期」と言われる。体力の衰えや脳の老化現象もはじまる。男も女も性ホルモンが減少し、疲労感や倦怠感、抑うつ症状といった「更年期障害」が生じる場合も少なくない。精神科医の和田秀樹氏は、こうした状況は「うつ病」になる可能性を高め、放置しておくと症状を悪化させてしまうと警鐘を鳴らす。うつ病にならないためには何をすべきか。「男性ホルモン」がカギを握っている。
(*)本稿は『50代うつよけレッスン』(和田秀樹著、朝日新書)の一部を抜粋・再編集したものです。
■和田秀樹の「50代うつよけレッスン」
(1)「うつ病」は50代が危ない!男性ホルモンの減少が記憶・判断力の低下、疲労感・不眠・イライラ・抑うつ感などを招く←いまココ
(2)50代になったら「肉」を食え!注射や塗り薬などで男性ホルモン補充もいいが、食生活でも若さを取り戻すには
(3)肉だけじゃない!ホルモンを活性化させる食べ物とは?がんやうつを予防するにはコレステロール値は下げてはいけない
性ホルモンの減少がもたらす影響
50代以降になると心身が大きく変化するため、自律神経が乱れ、日常的に不安を感じやすくなります。その結果、うつ病になる人も増えるわけですが、普段から物ごとの捉え方や考え方をうつになりにくいものへ変えていくと同時に、生活リズムや食事、運動など、うつ病になりにくい生活習慣を身につけることも重要です。
特に重要なのが、ホルモンバランスを整えることです。
性ホルモンは人間の精神状態に大きな影響を及ぼします。
たとえば、女性の場合は、妊娠中や出産後、ホルモンの急激な変化や出産によるストレスや疲労によって、うつ的な症状が出やすくなる「産後うつ」になる人が一定数います。過度な落ち込みや不安、不眠、気力減退、興味や喜びを感じなくなるなどの症状が続き、母子のどちらにも深刻な影響を及ぼすことがあります。
 和田 秀樹(わだ・ひでき) 1960年、大阪府生まれ。精神科医。立命館大学生命科学部特任教授。1985年、東京大学医学部卒業。長年にわたり高齢者医療の現場に携わっている。主な著書に、『感情的にならない本』(PHP文庫)、『70歳が老化の分かれ道』(詩想社新書)、『80歳の壁』(幻冬舎新書)、『プラグマティック精神療法のすすめ』(金剛出版)、『70代から「いいこと」ばかり起きる人』『自分が高齢になるということ』(共に朝日新書)、『疎外感の精神病理』(集英社新書)など多数。
和田 秀樹(わだ・ひでき) 1960年、大阪府生まれ。精神科医。立命館大学生命科学部特任教授。1985年、東京大学医学部卒業。長年にわたり高齢者医療の現場に携わっている。主な著書に、『感情的にならない本』(PHP文庫)、『70歳が老化の分かれ道』(詩想社新書)、『80歳の壁』(幻冬舎新書)、『プラグマティック精神療法のすすめ』(金剛出版)、『70代から「いいこと」ばかり起きる人』『自分が高齢になるということ』(共に朝日新書)、『疎外感の精神病理』(集英社新書)など多数。
また、40代、50代の更年期と言われる時期にもホルモンバランスが崩れて自律神経系の不調が起こり、疲労感や倦怠感、のぼせや冷え、多汗、動悸などのほか、頻尿や残尿感、肩こりや関節炎、血圧の乱高下をもたらすことがあります。
仕事や家事などの日常生活に支障をきたして、婦人科で更年期障害の診断を受ける人も少なくありません。
男性の場合、男性ホルモン(テストステロン)のピークは20代で、その後はゆるやかに減少し続け、70代以降になれば女性よりも分泌量が低くなります。
男性ホルモンは主に性機能を高める働きが有名ですが、それ以外にも、筋肉量を増やしたり、内臓脂肪が増えるのを抑えたり、動脈硬化を防ぐなど、さまざまな役割を担っています。ですから、加齢で男性ホルモンが減ってくると、体にさまざまな影響が出てきます。