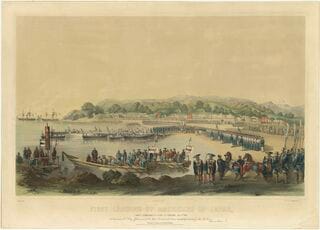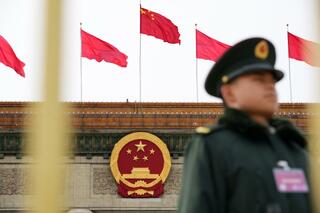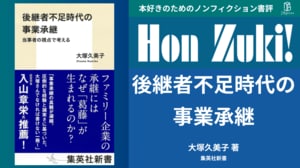この日の刑事課当直員は、強行犯係の係長(警部補)が班長をつとめ、あとは私と後輩刑事(巡査)の3名だった。通報のあった病院に急行した班長と私は、捜査車両を病院内の駐車場に止めてICU(集中治療室)に向かう。

正面玄関から病棟に入ると1階の受付フロアに、喪服を着た男女の人だかりができていた。24時間体制で救患を受け入れている総合病院とはいえ、さすがに喪服の集団は違和感がある。
受付カウンターの前に立つと、私は女性事務員に警察手帳を見せながら要件を伝える。
「先ほど、こちらの病院から署に検視の要請がありましたので、まいりました」
「はい、お待ちしておりました。じつは、私どもも社員の方が突然大勢いらっしゃったので困っていたところでして・・・」
喪服の集団に目を向けて、事務員は声を落とす。
検視を要する異状死と、その死にあわてふためく大勢の社員たち――。この状況から、遺体を見るまでもなく事件のにおいを感じる。
私は自分の中にある刑事のスイッチを入れ直した。
全身に皮下出血
検視対象の男性(47歳)の遺体は、病室のベッドに横たわっていた。
病室には、喪服姿の遺族らしき女性たちの姿もあった。ひとりは若く、20歳そこそこ。顔に白い布をかぶせられた遺体のかたわらで、立ちつくして泣いている。
そのとなりでは、40代の女性が丸椅子に座ってうつむいていた。ふたりは男性の娘と妻のようだ。
「いまから、警察がご遺体を調べさせていただく『検視』を行います」
このように宣言したあと、私は異状死の扱いについても説明する。
「この病院の先生はご主人の主治医ではないので、『死亡診断書』の作成ができません。今回の場合は警察が検視して、警察の委託医師(大阪市内なら監察医)が死亡診断書に代わる『死体検案書』を作成できるかどうか判断します」
「死体検案書」とは、医師の診療を受けずに亡くなった死体を検案し、死亡を確認した医師が発行する証明書のことだ。遺体に外傷などがあれば事件性があるため、死因を究明するために司法解剖の手続きを踏むことになる。