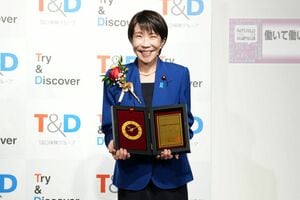いまだになくならない就活セクハラ(写真はイメージ、milatas/Shutterstock.com)
いまだになくならない就活セクハラ(写真はイメージ、milatas/Shutterstock.com)
(川上 敬太郎:ワークスタイル研究家)
セクハラ防止が義務づけられているのは「雇用している社員」のみ
「女子学生に酒を飲ませて性的暴行を行った」
「OB訪問にかこつけて自宅に連れ込んだ」
これら犯罪行為にまで発展したケースが報じられたことで、就職活動の際に学生が受けるセクシュアルハラスメント、いわゆる“就活セクハラ”への問題意識は一気に高まりました。
いかなる相手、状況においてもセクハラは卑劣な行為に違いありません。長く過ごしてきた学生時代に別れを告げ、不安と期待を胸に抱きながら、まさに社会に出る一歩を踏み出そうとした矢先にセクハラを受けてしまうとなれば、その衝撃は察するに余りあります。
いま、政府は就活セクハラの防止策を会社に義務づける方向で検討しています。ただ、法律で義務づけるまでもなく、セクハラが問題であることはすでに世の中に周知されているはずです。それなのに改めてフォーカスされている就活セクハラには、どのような特徴があるのでしょうか。
冒頭で指摘したように、犯罪行為にまで発展している悪質なケースが報じられたことは、就活セクハラの存在が広く知られるようになった大きなきっかけの一つです。また、加害者が住友商事や大林組、近鉄グループといった大手有名企業の社員だったことも注目を集める要因になりました。
セクハラという言葉が世に知られるようになり、流行語大賞に選ばれたのはおよそ36年も前。2007年には男女雇用機会均等法によって、セクハラ防止のための措置が10項目にわたり会社に義務づけられました。しかしながら、その対象は雇用している社員のみです。就活中の学生や求職者については同様の方針を示すことが望ましいとされているだけで、義務にはなっていません。