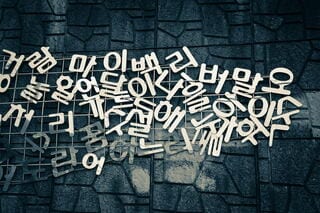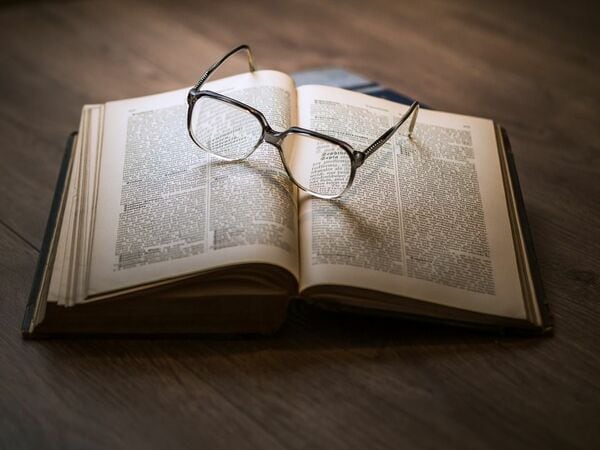 写真はイメージです(出所:Pixabay)
写真はイメージです(出所:Pixabay)
若手社員はなぜ会社を辞めるのか? 入社して数年で、あるいは30代前後で転職を経験した人たちを、元新聞記者の大学教員、韓光勲氏が紹介する連載「若手が会社を辞めるとき」。「若手社員が辞める理由」と「辞めた若手社員はどこへ行ったのか」を明らかにしていく。(JBpress)
(韓光勲:梅花女子大学文化表現学部国際英語学科 専任講師、社会学研究者)
これまで何人かの転職経験談を紹介してきたが、今回は筆者自身の経験談を述べたい。
今年(2025年)4月から、大阪府にある梅花女子大学で専任講師として働くことになった。大学教員の世界では就職難がいわれる中、とてもありがたいことである。
連載の第1回(「憧れて入社した会社の「耐え切れない」働き方、有望な若手記者はなぜ新聞社を去ったのか?」)で書いたように、筆者は大学院の修士課程を卒業後に新聞記者となったが、激務が重なり、さらに旧態依然とした新聞社の体質に我慢がならず、わずか3年で新聞社を辞めた。
新聞社を辞めたのは2022年7月末。新聞記者を諦め、研究者の道に進もうと考えた。翌年3月まで失業手当をもらいながら、大学院博士課程への進学を準備した。
大学教員になる方法を知るため、関連書籍はあらかた読んだ。鷲田小彌太氏の『大学教授になる方法』(PHP研究所)を読んだが、出版されたのが1995年とひと昔前の本なのでほとんど参考にならなかった。
それよりも、市役所職員から哲学研究者になった小川仁志氏の『市役所の小川さん、哲学者になる 転身力』(海竜社)、官僚から大学教員になった中野雅至氏の『1勝100敗! あるキャリア官僚の転職記~大学教授公募の裏側』(光文社)や『ビジネスマンが大学教授、客員教授になる方法』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)といった本が参考になった。
これらの本に書いてあるのはごくごく当たり前のことで、「大学教員になるためには優れた学術論文を書かなければならない」ということである。「優れた学術論文」とは、つまり「学会誌に掲載された査読付き論文」である。