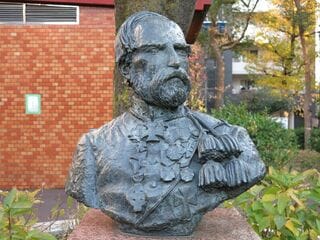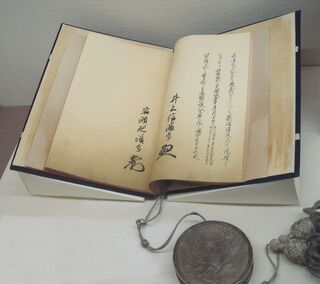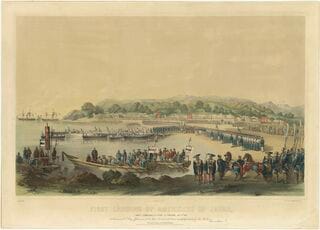中岡慎太郎とは、どのような人物なのか?
 中岡慎太郎の生家(復元) 写真=フォトライブラリー
中岡慎太郎の生家(復元) 写真=フォトライブラリー
ギャラリーページへ
最初に、中岡慎太郎について、簡単に紹介しておこう。中岡は、言わずと知れた筋金入りの幕末の尊王志士である。土佐国安芸郡北川郷(高知県北川村)の大庄屋である小伝次
残り1811文字
 中岡慎太郎の生家(復元) 写真=フォトライブラリー
中岡慎太郎の生家(復元) 写真=フォトライブラリー
最初に、中岡慎太郎について、簡単に紹介しておこう。中岡は、言わずと知れた筋金入りの幕末の尊王志士である。土佐国安芸郡北川郷(高知県北川村)の大庄屋である小伝次
残り1811文字
ここからは、JBpress Premium 限定です。
カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら