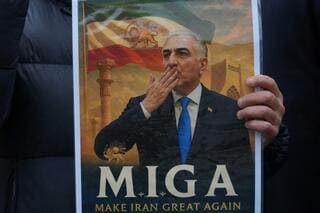後出しの女帝・小池都知事が打ち出した「無痛分娩費用の助成」が図らずも迫る産科の重い選択
【無痛分娩に対応している施設は4分の1】都知事選の公約筆頭に現場は「条件付きYES」だが、超えるべき高いハードル
2024.6.22(土)
ここからは、JBpress Premium 限定です。
カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら
あわせてお読みください

「事業仕分け」の再現狙う? 東京都知事選、蓮舫の公約「ガラス張りの都政」に透ける“東京版・仕分け”への意欲
公約を徹底分析!「都政継続vs政権交代」「劇場型vs突破型」「バラマキvs事業仕分け」
白鳥 浩

1歳未満の小型犬の90%が歯周病、そんな不安につけ込む脱法歯石除去に動き出した当局
【無資格の歯石除去は違法】京都府警がドッグカフェ摘発、農水省が初めて「クロ」の見解を出した理由
星 良孝

70代のタクシー運転手の半数に視野などの異常、運転手を対象にした初の眼科検診で明らかになった不都合な事実
交通事故の背景としてリスクが高まる「緑内障」、眼底検査が鍵を握る
星 良孝

東京都知事選、小池百合子と蓮舫が“似て非なる”4つの理由…「クールビズ」「2位じゃダメ」に見る2人の違いとは?
「初代WBSキャスター」と「第14代クラリオンガール」、2人ともとにかく目立つ女性政治家だが…
白鳥 浩

【出生率が過去最低1.2に】なぜ少子化は止まらない?性愛格差、重い税負担…橘玲氏、楡周平氏、森永康平氏らに聞く
JBpressイチオシの少子化記事5選
湯浅 大輝
本日の新着
日本再生 バックナンバー

【関連銘柄も爆上がり】2035年に6兆円市場に、AI業界が注力するフィジカルAI、日本はロボット大国の地位を守れるか
小林 啓倫

「連休で仕事が休みになっちゃって。3000円くらい貸してもらえませんか」大型連休で干からびる派遣高齢者の日常
若月 澪子

いまさら?軍民両用物資の対日輸出規制、何が該当するかは中国当局が判断、品目リストの明示なく超絶イライラ
山本 一郎

「墓じまい」と「家じまい」に踏み切った徳川慶喜家、歴史上の著名人の墓が墓じまいされるのはなぜか?
鵜飼 秀徳

「地震リスクが世界一大きい」とされる浜岡原発のデータ不正、危険な原発を「安全」にすり替える悪質な体質
添田 孝史

気象庁・元地震火山部長が東電裁判の裁判官に憤慨、「科学に向き合わないその態度はまるでガリレオ裁判の裁判官」
添田 孝史