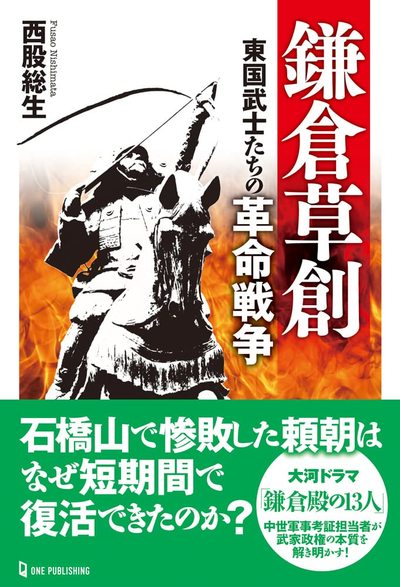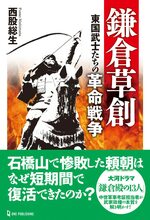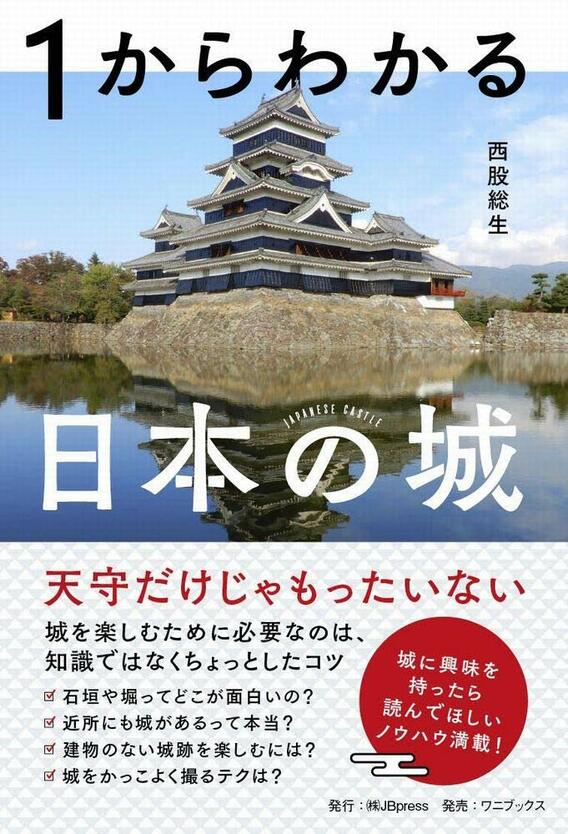津軽鉄道の「走れメロス号」撮影/西股 総生(以下同)
津軽鉄道の「走れメロス号」撮影/西股 総生(以下同)
(歴史ライター:西股 総生)
心の中の「裏切り」
(前編から)『走れメロス』の物語を、セリヌンティウスの立場から考えてみよう。作中では彼とメロスとの関係は、「竹馬の友」とあるだけで具体的には書かれていない。おそらくメロスとは同郷だったが、街に出て身を立てているのだろう(作中には石工とある)。
つまり、物語の時点では、セリヌンティウスはシティボーイなのである。村の羊飼いであるメロスとは、立場も生活スタイルも違う。そして、都会人に対する田舎者のコンプレックスというのも、太宰作品にしばしば現れるモチーフなのだ。
 冬の津軽鉄道。太宰の故郷は冬は雪深い田野だった
冬の津軽鉄道。太宰の故郷は冬は雪深い田野だった
セリヌンティウスは、はたしてメロスを心からの親友と思っていただろうか。暑苦しいやつだけど、まあ面白いところもあるし、昔のよしみもあるから、たまに街へ出てきたときくらい付き合ってやるか、くらいの認識ではなかったか。
そもそも、いきなり王宮に連行されて人質として牢に入れられたのである。メロスを恨み呪うのが、普通ではないか。「あのバカ、わけのわからん事件に巻き込みやがって … あ、でも、あいつ正真正銘のバカだから、本当に刻限までに戻ってきそうではあるなあ … 」というあたりが、本音ではなかったか。
そうして、メロスが戻ってこなかった場合の言い逃れと、本当に戻ってきた場合の自分の振る舞い方と、両方を獄中で考えていたのではなかったか。戻ってきた場合は、感動の対面を演出すれば、自分は街のヒーローになれるではないか。作中の最後、感動の対面で「私はこの三日間、たった一度だけ、ちらと君を疑った」というセリヌンティウスの告白は、きれい事すぎるように思うのだ。
 三鷹市内を流れる玉川上水。太宰と山崎富栄が入水したあたり
三鷹市内を流れる玉川上水。太宰と山崎富栄が入水したあたり
一方のメロスも途中で一度、自暴自棄になって走ることを投げ出してしまう。この場面の迫真性こそ、筆者は太宰文学の本領ではないかと思う。情熱が極限まで高まったところで、急に気持ちが萎えて冷めてしまうという心理の動きは、末期のやるせない短編『トカトントン』で徹底的に描かれたものだ。
『走れメロス』の真のテーマは「裏切り」ではないだろうか。露見を免れ、なかったことにされた、心の中の「裏切り」。偽善的に取り繕われた日常の背後で、誰しもが心の中に持っている、後ろ暗い「裏切り」。それこそは太宰が書きたかった、いや、書かざるをえなかった人間の性(さが)ではなかったか。このテーマこそ、代表作の『人間失格』や『ヴィヨンの妻』に通じるものである。
 三鷹の禅林寺にある太宰の墓。今も献花が絶えない
三鷹の禅林寺にある太宰の墓。今も献花が絶えない
以上のように考えてきたとき、『走れメロス』のラストシーンのもつ意味が、はっきりと浮かび上がる。メロスとセリヌンティウスと王とが、三人手を取り合って感動に暮れるシーンは、どう割り引いて読んでも、くさい。
そのくささの中で、一人の少女が恥ずかしそうに、メロスに布を差し出す。濁流を泳ぎ山賊と戦ううちに、メロスはいつしか(なぜか)全裸になっていたのだ。でも、濁流を泳いだり山賊と戦ったりしたからといって、裸になる必然性があっただろうか。なぜ作者は、最後にこんな恥ずかしいシーンを用意したのだろうか。
セリヌンティウスは、メロスに布をまとうように朗らかに促し、メロスも自分が全裸であったことに気付いて恥じる。かくて、「恥部」は隠されたのである。「裏切り」を、なかったものとして取り繕うアイテムとして、布は差し出されなければならなかったのだ。
とまあ、以上が筆者の個人的解釈である。あなたは、どうお考えだろうか。この際だから、太宰治の不朽の名作『走れメロス』を、もう一度「大人の読書」としてじっくり味わってみては、いかがだろう。
 三鷹駅近くにある太宰治文学サロン。近年は海外から訪れるファンも少なくないという
三鷹駅近くにある太宰治文学サロン。近年は海外から訪れるファンも少なくないという
[参考図書]拙著 『鎌倉草創-東国武士たちの革命戦争』(ワンパブリッシング)は、鎌倉幕府の成立を描いた歴史書ですが、書中のコラムで太宰の『右大臣実朝』に触れています。ご興味のある方はぜひ、ご一読を。