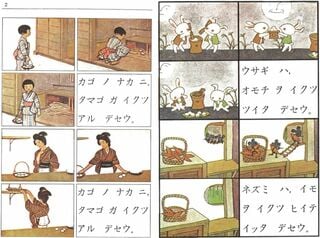東京高裁で再審決定が下されインタビューを受ける袴田秀子さん(2023年3月13日、写真:山口フィニート裕朗/アフロ)
東京高裁で再審決定が下されインタビューを受ける袴田秀子さん(2023年3月13日、写真:山口フィニート裕朗/アフロ)
5月23日、いわゆる「袴田事件」に対する再審公判で、絞首刑が確定しつつ執行停止、釈放されている「袴田巌氏(87、1936-)」に対して、検察側が改めて「死刑」を求刑、社会に様々な反響が広がっています。
といっても「検察の言う通りだ」という反響は目にしません。
冤罪事件の顛末と、それを引き起こした司法の構造的な腐敗に対して、複数の批判が加えられているということです。
本件、私が2004年から8年ほど、身近なお手伝いをさせていただいた元最高裁判事・東京大学法学部の團藤重光名誉教授(1913-2012)がお元気であったなら、間違いなくおっしゃったであろう(と私が考える)ポイントを、私の文責で記したいと思います。
一言でいうなら「可謬性」。
人は間違えることがあるという現実に対して、「無謬神話」を誇るような組織は、裁判所であれ検察であれ必ず腐る。
それへの本質的な対策は、風通しを良くすることしかないというのが、「團藤説」のポイントです。
まず、事件を振り返るところから始めてみましょう。
通称「袴田事件」とは
通称「袴田事件」とは、1966年6月30日、静岡県清水市で味噌製造会社の専務一家4人が殺害、集金袋が強奪され、家屋が放火された強盗殺人・放火事件を指します。
本稿執筆時から数えれば58年前の出来事です。
2008年3月、第1次再審請求は最高裁により特別抗告が棄却されますが、同年4月、直ちに第2次再審請求が行われ、2014年3月27日、静岡地裁は再審開始と袴田氏の死刑ならびに拘置の執行停止を決定(「村山決定」)。
同日午後、袴田氏は48年ぶりに東京拘置所から釈放されましたが、長年にわたる拘禁疾患から、元の精神状態ではない形での解放でした。
その後、村山決定を不服とする検察側は東京高裁に即時抗告。
高裁の大島隆明裁判長は再審請求を棄却しますが(大島決定)、弁護側は最高裁に即時抗告します。
最高裁第三小法廷(林道晴裁判長)は高裁差し戻しの判決。
さらに「単に差し戻して時間を無駄にするのではなく、直ちに再審を開始すべき」という意見まで付されての差し戻しでした。
最終的に昨2023年3月、東京高裁(大善文男裁判長)は検察の即時抗告を棄却(大善決定)。
同10月に静岡地裁で袴田事件の再審初公判が開かれ、無罪を主張しますが、検察側はあくまで「有罪」を主張、先週の「死刑求刑」に至ったわけです。
現在、検察側でこの問題を担当している検事が誰で、何歳であるか知りません。
しかし、袴田事件が発生した時点では生まれていなかった可能性が高く、袴田氏の死刑確定(1980年)時点では司法試験に合格していなかったと思われます。
というのも、現在の検事総長、甲斐行夫氏(1959-)にしてから1982年に東京大学法学部卒業、83年に札幌地検任官で、袴田事件の死刑確定から4年後にようやく法曹になっている。
すでに教科書に印刷された歴史的事件として、ハカマダの名を見た新人が、今現在は検察トップとして司直を率いている状況なのです。
では、どうしてここまで・・・つまり、自分が生まれる前に発生し、事件の詳細など最終的には分かるわけもない事件に対して、検察は「死刑」に固執するのか?
それは検察という組織が持つ「無謬神話」と、それに追随しないと出世の階段を昇れなくなる「役所」としての組織の内在論理が絡まりあった最低最悪の腐敗構造が深因となっている・・・というのが、團藤先生が御元気だったら、必ずなさったであろう、ご批判の本質的なポイントです。
さらに言えば、この「無謬神話」を建て前とする組織腐敗は「検察」だけでは全くない。
「裁判所」から「警察」まで、あらゆる役所、あるいは役所大学であるところの東京大学なども、無謬はおろか、「トンでも事件」山積の現実があります。
しかし、建て前上「王様はハダカではない」と強弁する、江戸時代もかくや、という封建メンタリティに支配されている。
これを脱却しなくては、21世紀の法治に未来はないとまで、團藤先生は折あるごとに厳しく指摘しておられました。