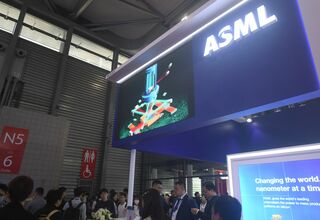談志は「落語は人間の業の肯定」と定義
談志は「落語は人間の業の肯定」という定義をし、そこから逸脱する人情噺については、生涯クエスチョンを投げ掛けていました。
とはいえ、「そんな小難しいことはいいから、談志ならうまくやってくれるさ」というファンの声を汲んで、「こういう噺でも俺は名人だ」とばかりに、昔ながらの名人芸を見事に演じていたものでした。
しかし、やはり談志にしてみれば、所詮、これは妥協策でした。
名人の系譜上の伝統的な名演は、談志からしてみれば本質的な解決には程遠いものと認識していたようで、「芝浜」=「業の克服」というネタに対して、生涯実験を施していました。
いやはや、これはまさに自縄自縛と言うべきものです。そんなの放置しておけばいいのにと思うのですが、そこがマルクスにも通じる談志の「しつこさ」だったのかもしれません。
弟子入りして以来、毎年年末が近づくと、「いやあ、名演だなあ」と思う「芝浜」に何度も接しましたが、それに満足することなく「いやあ、まだよくなる。もっともっと」と叱咤激励する姿には、こちらが怖くなったものでした。
が、そんな苦闘し続ける談志を、神様は見捨てませんでした。
その瞬間は、談志の晩年に訪れたのです。
これが先ほども書きましたが、談志マニアの間で語り草になっている、2007年12月18日のよみうりホールの「芝浜」です。
亡くなる四年前、もうそろそろ本人も、従来の熱演型の落語からフェイドアウトしていくことになるだろうなという実感というか、予感はあったはずです。
「年取っていいことなんか、ねえ」と、このころ頻繁に口にしていたものでした。
自ら「ミューズが舞い降りた」と言わしめた「芝浜」には、私は立ち合えませんでしたが、後日、映像で観ると、これまで築き上げてきた己の落語理論なんざどうでもいい、と言わんばかりの圧倒的な高座でした。
これぞまさにアウフヘーベン! 談志の存在、理論からルサンチマンすらまで、すべてを総合したような「芝浜」に鳥肌が立ちました。登場人物、特に女房が吹っ切れているのです。まさに、この怪演を成し遂げるために、苦難続きの落語旅を続けてきた談志への、最期のご褒美のようにすらも思えてきました。
これこそ、まさに「他の商品と取り替えようがない存在」として屹立している「貨幣」そのものではないかと、いましみじみ感じています。