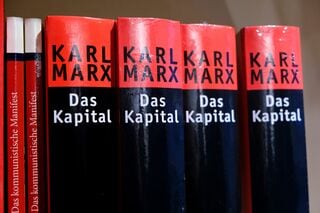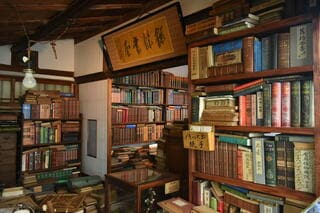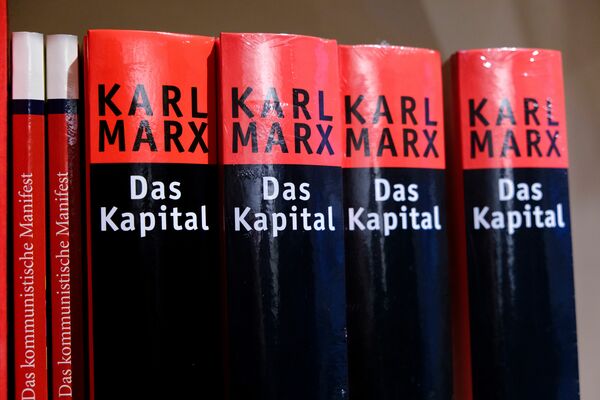 カール・マルクスの「資本論」(写真:Alexandros Michailidis/Shutterstock.com)
カール・マルクスの「資本論」(写真:Alexandros Michailidis/Shutterstock.com)
- カール・マルクスの『資本論』を落語で読み解く・・・そんな「無謀」な試みに、慶応大学でマルクス経済学を専攻した落語家・立川談慶師匠が挑んだ。
- 談慶師匠いわく、江戸時代に生まれた落語は「資本主義の到来を予見していた」という。一体どういうことか。
- 著書『落語で資本論 世知辛い資本主義社会のいなし方』(立川談慶、日本実業出版社)から一部を抜粋し、3回にわたって連載する。第2回は、驚きの発想が笑いを誘う「開帳の雪隠」から「イノベーション」を読み解く。日本を代表するマルクス経済学者・的場昭弘氏の解説付き。
【連載「落語で資本論」】
第1回:資本主義は「鰻」と同じ? その心は「どこに向かうか誰にもわからない」
第2回:公衆便所でひと儲け! 江戸っ子が考えたビジネスモデルに見る現代の企業
第3回:立川談志は落語界の「貨幣」だ! マルクスのような「しつこさ」で代替不能
イノベーションとしての「開帳の雪隠」
ジョン・ステュアート・ミルは、その『経済学原理』の中で言っている、「すべての従来なされた機械の発明が、何らかの人間の日々の労苦を、軽減したかどうかは疑問である」と。(注・省略)
しかし、かようなことは、決して、資本主義的に使用される機械装置の目的ではないのである。労働生産力のすべての他の発展と同じく、機械装置は、商品を低廉にするためのものであり、また、労働者が自分自身のために必要とする労働日部分を短縮して、彼が資本家に無償で与える他の労働日部分を延長するためのものなのである。機械装置は、剰余価値の生産のための手段である。
生産様式の変革は、工場手工業(マニュファクチャ)にあっては労働力を、大工業にあっては、労働手段を出発点とする。したがって、まず第一に研究すべきは、何によって労働手段は、道具から機械に転化されるか、あるいは、何によって機械は、手工用具から区別されるか、ということである。ここで考えられるのは、大きな一般的な諸特徴だけである。社会史の諸時代も、地球史のそれと同じく、抽象的な厳密な限界線によっては、区画されないからである。(マルクス『資本論』第1巻13章)
こんな小噺(こばなし)があります。
男2人が会話している。
「おい、1万円以上の値打ちのある儲け話があるんだけど、聞きたい?」
「1万円? 必ず儲かるのか?」
「ああ」
「わかったよ」
と言って、男はその男に1万円を払います。
「おい、本当に儲かるんだよな。教えてくれよ」
男はその1万円を懐にしまいながら、笑って言いました。
「いま、俺がやったのと同じことを他所でやればいいんだよ」
くだらないながらも、よくできていますよね。
冒頭のジョン・スチュワート・ミルが暴いた真理もこれじゃないかと思うのです。
つまり、機械を導入して得られた利益は、その機械が一般的に行き渡るようになってしまえば、儲からなくなるということです。資本家は慈善事業で資本を動かしているわけではないのです。機械の導入により、労働者の労苦は軽減したとしても、同時に労働者の単価(時給)が安くなるだけです。労働者の単価(時給)が安くなったら、同じように「労働力の再生産費=給料」も結果として安くなるだけなのです。そして、みんな(他の事業者)が機械の導入にシフトしてゆけば、結果として同業者に真似されることになり、ありきたりな平凡な光景へと落ち着いていくだけなのです。