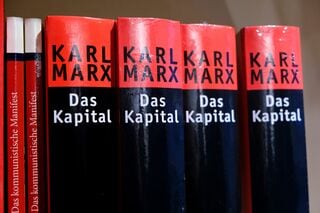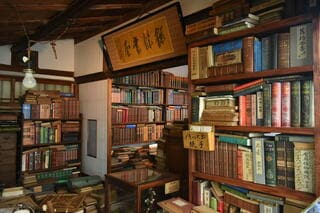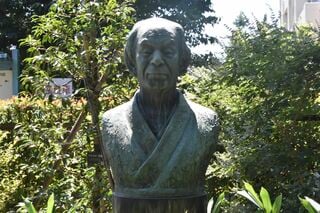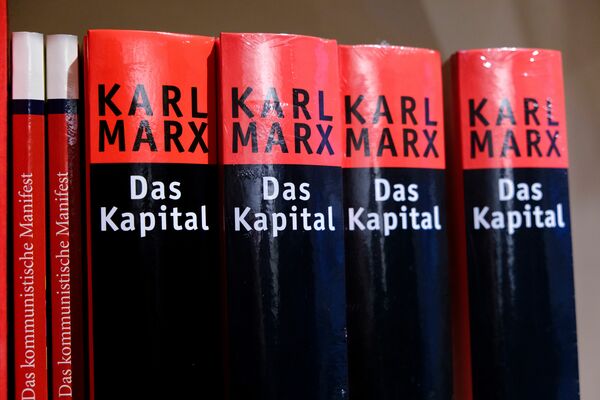 カール・マルクスの「資本論」(写真:Alexandros Michailidis/Shutterstock.com)
カール・マルクスの「資本論」(写真:Alexandros Michailidis/Shutterstock.com)
- カール・マルクスの『資本論』を落語で読み解く・・・そんな「無謀」な試みに、慶応義塾大学でマルクス経済学を専攻した落語家・立川談慶師匠が挑んだ。
- 談慶師匠いわく、江戸時代に生まれた落語は「資本主義の到来を予見していた」という。一体どういうことか。
- 著書『落語で資本論 世知辛い資本主義社会のいなし方』(立川談慶、日本実業出版社)から一部を抜粋し、3回にわたって連載する。第3回は、落語の中でも特に有名な「芝浜」から「貨幣」を読み解く。日本を代表するマルクス経済学者・的場昭弘氏の解説付き。
【連載「落語で資本論」】
第1回:資本主義は「うなぎ」と同じ?どこに向かうか誰にも分からない
第2回:公衆便所でひと儲け!江戸っ子が考えたビジネスモデルに見る現代の企業
第3回:立川談志は落語界の「貨幣」だった?マルクスのような「しつこさ」で代替不能
「芝浜」の貨幣論
貨幣(カネ)というのは非常に悩ましいものであります。無ければ辛いし、かといってそればっかりだと貧乏くさくなって、非常に距離の取り方の難しい存在です。
いつだったか『男はつらいよ』で寅さんが、「俳句に『それにつけてもカネの欲しさよ』とくっ付ければ短歌になる」というようなセリフを言うシーンがありました。つまり、俳句(五・七・五)に、下の句として「それにつけても・カネの欲しさよ(七・七)」を付ければ形式的にも、意味的にも短歌(五・七・五・七・七)として成立するということですが、いやはや、庶民の心と、俳句、短歌のある種の特性(通俗性)を見事に捉えた名セリフだと思いました。
落語にもやはり「カネ」を扱った物語が多数あります。年末になるとまるで「第九」(ベートーヴェンの交響曲第九番《合唱》)を求めるのと同じようにお客さんも聞きたくなり、そして落語家もこぞってやりたがる「芝浜」もそんな一席です。
 立川談慶(たてかわ・だんけい) 落語家。
立川談慶(たてかわ・だんけい) 落語家。立川流真打ち。1965年、長野県上田市生まれ。慶應義塾大学経済学部でマルクス経済学を専攻。卒業後、株式会社ワコールで3年間の勤務を経て、1991年に立川談志18番目の弟子として入門。前座名は「立川ワコール」。二つ目昇進を機に2000年、「立川談慶」を命名。2005年、真打ちに昇進。慶應義塾大学卒で初めての真打ちとなる。著書に『教養としての落語』(サンマーク出版)、『なぜ与太郎は頭のいい人よりうまくいくのか』(日本実業出版社)、『いつも同じお題なのに、なぜ落語家の話は面白いのか』(大和書房)、『大事なことはすべて立川談志に教わった』(ベストセラーズ)、『「めんどうくさい人」の接し方、かわし方』(PHP文庫)、小説家デビュー作となった『花は咲けども噺せども 神様がくれた高座』(PHP文芸文庫)、『落語で資本論 世知辛い資本主義社会のいなし方』など多数の“本書く派”落語家にして、ベンチプレスで100kgを挙上する怪力。
【あらすじ】
腕はいいものの、大酒飲みの魚屋の勝こと魚勝が主人公です。これも江戸っ子の粋がりなのでしょう。「なあに、酒食らって休んだってすぐ元が取れるんだ」という気概こそ江戸っ子の本質、相も変わらずの貧乏暮らしです。1カ月半も商いを休む体たらくに業を煮やした女房は、朝早く魚勝を起こし、芝の魚市場に仕入れに向かわせます。ところが女房が時間を間違えてしまっていたようで、河岸(魚市場)は開いていません。
仕方なしに煙管を吸って時間をつぶしていると、波打ち際に革の財布を見つけます。拾って中を見ると、大金(談志は42両)が入っています。大喜びの魚勝は家に帰って、「生涯働いても稼げるカネじゃねえ」と、「お上に届けよう」という女房を説き伏せたうえ、「もう働かねえぞ」と飲み仲間を集めて大酒を食らいます。
翌日、女房は亭主を叩き起こして「商いに行って」と催促します。亭主は拾った財布の金で何とかしろと言いますが、女房は「知らないよ、お金なんて。そもそも魚河岸なんか行ってないだろ。お前さんが金欲しさのあまりに財布を拾った夢を見たんだろ」と言い返します。
「俺は間違いなく拾った!」と言い争いになり、ついに女房は泣き出して、「どうせなら拾った夢じゃなく、稼いだ夢を見てよ」と訴えるのでした。
とうとう魚勝は「あれは夢だった」と信じ込み、「これじゃいけねえ」とそれ以降、酒を断って、必死に働き始めました。
その3年後──。表通りに小さいながらも店を構え、弟子の3人も置くような身分になった魚勝でした。
そしてその年の大晦日の晩のことです。女房は財布の話を切り出します。「あれは夢じゃなかったの」と号泣しながら、真相を打ち明けます。