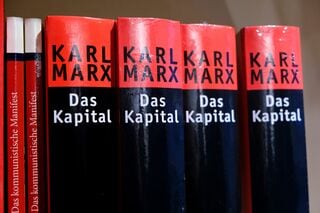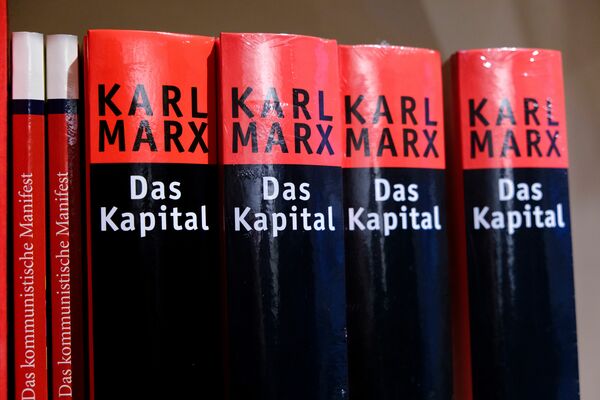 カール・マルクスの「資本論」(写真:Alexandros Michailidis/Shutterstock.com)
カール・マルクスの「資本論」(写真:Alexandros Michailidis/Shutterstock.com)
- カール・マルクスの『資本論』を落語で読み解く・・・そんな「無謀」な試みに、慶応大学でマルクス経済学を専攻した落語家・立川談慶師匠が挑んだ。
- 談慶師匠いわく、江戸時代に生まれた落語は「資本主義の到来を予見していた」という。一体どういうことか。
- 著書『落語で資本論 世知辛い資本主義社会のいなし方』(立川談慶、日本実業出版社)から一部を抜粋し、3回にわたって連載する。第1回は、うなぎを捕まえる仕草が笑いを誘う「素人鰻(しろうとうなぎ)」から「労働」を読み解く。日本を代表するマルクス経済学者・的場昭弘氏の解説付き。
【連載「落語で資本論」】
第1回:資本主義は「鰻」と同じ? その心は「どこに向かうか誰にもわからない」
第2回:公衆便所でひと儲け! 江戸っ子が考えたビジネスモデルに見る現代の企業
第3回:立川談志は落語界の「貨幣」だ! マルクスのような「しつこさ」で代替不能
労働力とは商品である──「素人鰻」
ある商品の消費から価値を引き出すためには、貨幣所有者は、流通圏内部すなわち市場においてその使用価値自体が価値の源泉となるような独特の性質を持つ商品を運良く発見する必要がある。その商品は現実にそれを消費すること自体が労働の対象化、すなわち価値創造となるような商品でなければならない。そして事実、貨幣所有者は市場でこのような特殊な商品を発見する──労働能力すなわち労働力がそれである。(マルクス『資本論』第1巻4章)
『資本論』が難しいのは、独特のレトリックと文体、そして聖書由来のキリスト教用語で書かれているからです(初めて読んだ大学三年の時なんざ、そのことにすら気づきませんでした)。
マルクスも談志も気難しいキャラで、無理矢理に共通項を見出すとすれば、「バカが嫌い」ということだったのではと思います。
談志は「人間のダメさ加減を認めるのが落語だが、俺は絶対バカな弟子は認めない!」と断言していました。ほんと面倒くさい人でした。
談志は「頭のいい奴が数人いればいい」と常々言っていたものです。そんな談志が頭の回転の速さを高く評価していたのが盟友の毒蝮三太夫(どくまむしさんだゆう)さんでした。「あいつはな、俺が言ったことに対して、見事に返してくるんだ」と絶賛していました。いつぞや、談志がレギュラーを務めていたテレビ番組があったのですが、共演者の中には談志の大嫌いな女性タレントさんがいました。談志はその女性タレントさんとかぶるのが嫌で、収録日も別にしてもらうほどでした。
 立川談慶(たてかわ・だんけい) 落語家。
立川談慶(たてかわ・だんけい) 落語家。立川流真打ち。1965年、長野県上田市生まれ。慶應義塾大学経済学部でマルクス経済学を専攻。卒業後、株式会社ワコールで3年間の勤務を経て、1991年に立川談志18番目の弟子として入門。前座名は「立川ワコール」。二つ目昇進を機に2000年、「立川談慶」を命名。2005年、真打ちに昇進。慶應義塾大学卒で初めての真打ちとなる。著書に『教養としての落語』(サンマーク出版)、『なぜ与太郎は頭のいい人よりうまくいくのか』(日本実業出版社)、『いつも同じお題なのに、なぜ落語家の話は面白いのか』(大和書房)、『大事なことはすべて立川談志に教わった』(ベストセラーズ)、『「めんどうくさい人」の接し方、かわし方』(PHP文庫)、小説家デビュー作となった『花は咲けども噺せども 神様がくれた高座』(PHP文芸文庫)、『落語で資本論 世知辛い資本主義社会のいなし方』など多数の“本書く派”落語家にして、ベンチプレスで100kgを挙上する怪力。
ある時、蝮さんが「何でそんなに嫌いなんだ?」と尋ねた時でした。談志は「あいつがそばに来るとな、俺のチンポが腐るような気がするんだ」と子供でも言わないようなことを口にしました。すると蝮さんは大笑いしながら、「そりゃ大変だな。向こうにしてみれば、あんまり他人には言えないような理由だもんな」と言った途端、談志は大爆笑したのです。
「なるほど、○○○(その女性タレント)が、『談志さん、私のこと嫌いなんですって。私がそばに寄るとチンポが腐るとおっしゃるの』とは確かに言えないわな。お前すごいな」と激賞していましたっけ。