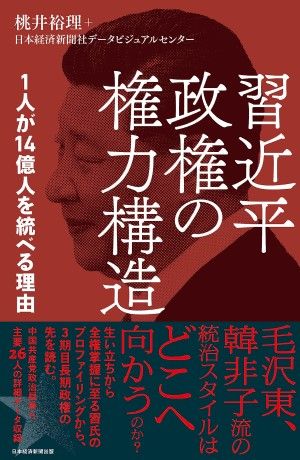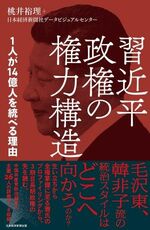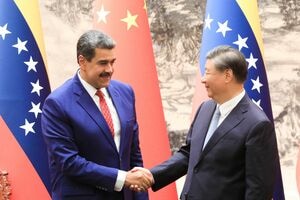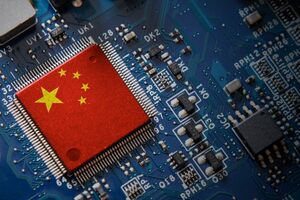習氏は生まれだけでなく、キャリアにおいても軍との関係が深かった。1979年に清華大学化学工程学部を卒業した後、最初に配属されたのは中央軍事委員会で、中央政治局委員・副首相・中央軍事委員会秘書長だった耿飈氏の秘書を務めた。習氏の経歴にはわざわざ「秘書(現役)」と記されている。文官ではなく、軍籍を持つ軍人という意味だ。要人の秘書であれば、軍の内部事情も垣間見ただろうし、様々な人物とも知り合って人脈も広げることができただろう。
福建省時代には、党幹部の仕事と軍務を兼任しながら、台湾海峡と対峙する福建省の軍人らと交流を深めた。そのころ結婚した彭麗媛夫人は人民解放軍所属の国民的人気歌手で、彭氏は現在も少将の肩書を持つ。結婚当時は地方の一幹部に過ぎなかった習氏が軍のスターと結婚できたのも、習氏が軍のプリンスだったからだろう。
軍との関係に苦労した江沢民と胡錦濤
一方、江沢民氏や胡錦濤氏は軍への基盤が皆無であったため、軍との関係構築には苦労した。
江沢民氏は、軍人らの歓心を買うことで軍の掌握を図った。軍事費を毎年10%近く増やし、軍人らにふんだんに予算と利権を与えた。海外では中国の急速な軍事費拡大に注目が集まったが、すべての予算が必ずしも効率的に軍備増強に使われていたわけではなかった。関連企業との癒着やサイドビジネスを通じ、軍人のポケットマネーに入る部分も少なくなかったためだ。裏金の一部は軍のポストの売買にも流れた。ポストを買って軍内の地位が上がれば、さらに大きな利権が手に入った。
江沢民氏はそうした状況を知りながら、幹部らの腐敗を放置したと同時に、多くの上将や中将を自らの手で抜擢し、江派のネットワークを軍内に構築していった。2002年に党総書記を引退した後も中央軍事委主席の座からは退かず、党と軍の実権を握って院政を敷いた。合計15年間にわたって軍のトップであり続けた。
続いて中央軍事委主席となった胡錦濤氏は江沢民氏以上に苦労した。党総書記に就任後、3年目にしてようやく主席の座を江氏から譲られたものの、軍は江派の牙城となっていた。しかも江氏の放任のもとで完全に党を軽視しており、「党の絶対的指導」からは程遠い状態だった。
胡錦濤氏は「軍を掌握できない党総書記」として政権基盤を確立することができず、最後まで江沢民氏の院政をはねのけることはできなかった。そのころ盛んに言われたのは、「政策は中南海を出ない(胡錦濤氏が政策を提案しても実現しない)」との言葉だ。開明的な政策を抱きながらも、一切実行できなかった胡錦濤政権の実態をよく表している。
江沢民氏や胡錦濤氏が辿った道筋と比較すれば、習氏のバックグラウンドがいかに恵まれていたかが実感できる。習氏は自身の優位性を生かしながら軍の抵抗勢力を抑え込み、2014年秋に「新・古田会議」の開催にこぎつけた。そこで軍の幹部らを前に「党への絶対服従」の徹底を宣言した。
福建省にある古田会議の史跡にいくと、毛沢東の写真に加え、習氏の写真や言葉がたくさん掲げられている。習氏は、毛沢東の伝説を上書きしたのだ。
習氏は1期目の5年間の間に、軍人らを従わせることにほぼ成功した。だが、その服従は粛清への恐怖ゆえの面従腹背であり、いつ覆るかはわからないものだった。そのため、2期目政権に向けては、軍人たちの忠誠を簡単には覆らないよう「制度」で固めることが作戦の中心となった。習氏は満を持して軍の大改革へと歩みを進めた。