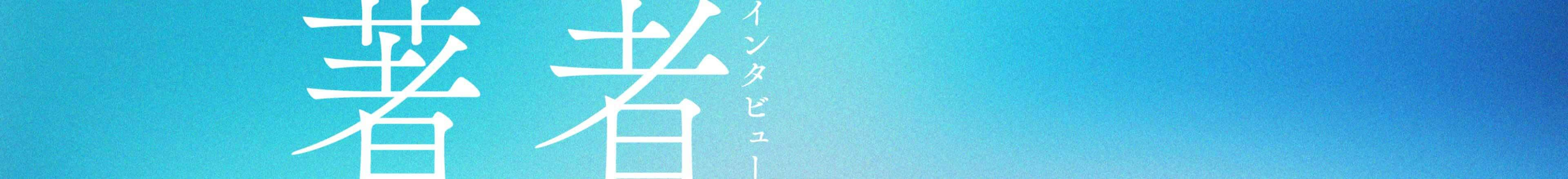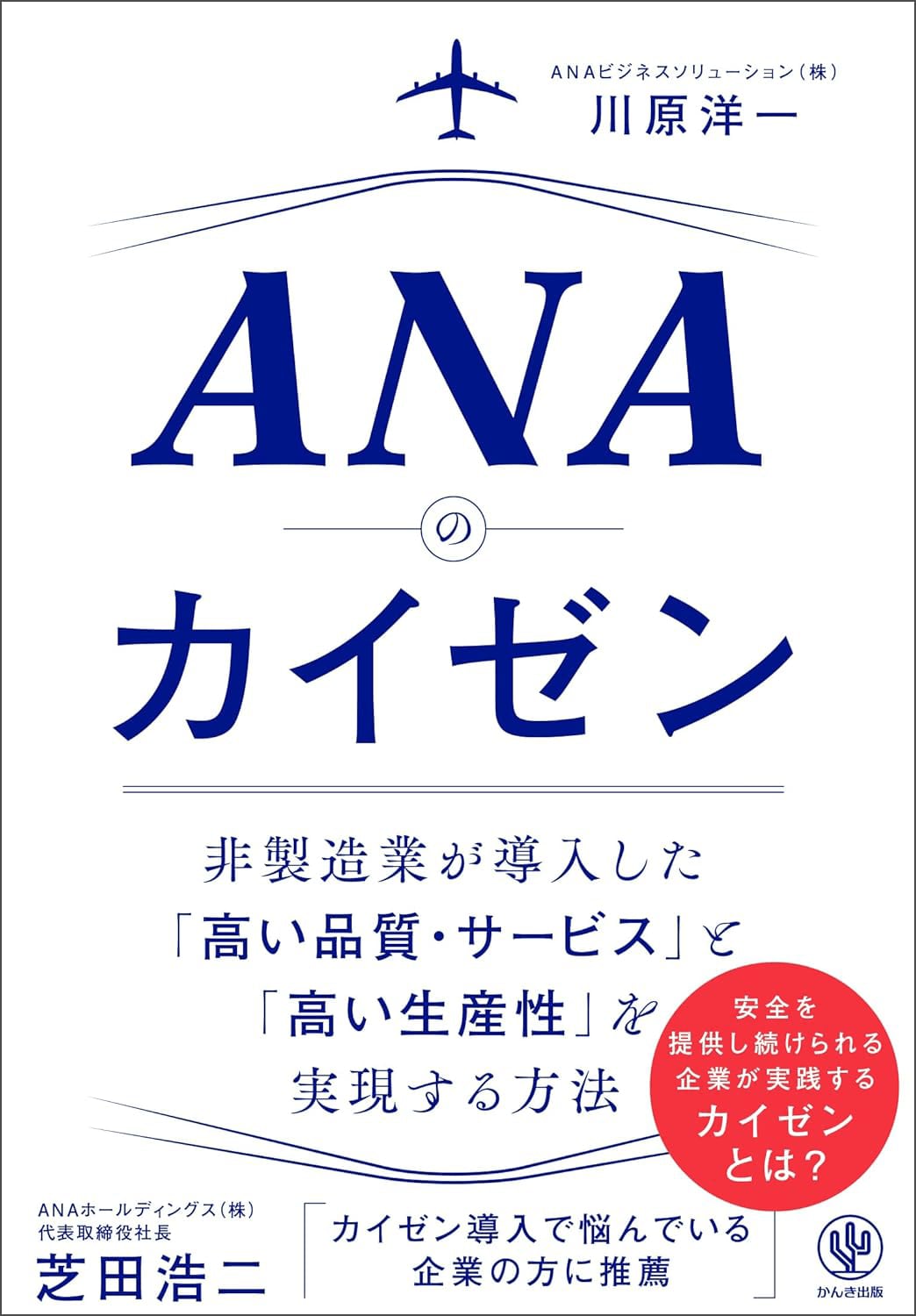出所:共同通信イメージズ
出所:共同通信イメージズ
トヨタ自動車発祥の「カイゼン」は、トヨタのみならず、さまざまなものづくりの現場で採り入れられている。そのカイゼンをグループ23社、約3万1000人を対象に展開したのが大手航空会社のANAだ。旅客・運輸サービスを主力事業とする非製造業の同社は、なぜカイゼンに取り組んだのか──。2024年12月に書籍『ANAのカイゼン』(かんき出版)を出版したANAビジネスソリューションの川原洋一氏に、ANAがカイゼンを導入した背景や、組織にカイゼン活動を定着させるためのポイントについて聞いた。
海外で活発に取り組まれている「KAIZEN」
──著書『ANAのカイゼン』では、2016年からカイゼンを導入したANAグループオペレーション部門の取り組みを主題としています。「カイゼン」とは、具体的にどのような取り組みを指すのでしょうか。
川原洋一氏(以下敬称略) 「改善」を辞書で引くと「悪いところを良くする」と説明されています。しかし、企業の取り組みを指す場合、漢字ではなくカタカナで「カイゼン」と表記することがほとんどです。これはカイゼンの概念を世に打ち出したトヨタ(トヨタ式カイゼン)の影響だと考えられます。
カイゼンには「現状に満足せず、今よりもっと良くし続けること」という意味が込められており、その活動に関わる一人一人が「今より良い状態にするにはどうすればよいか」と考える意思が重要視されています。
昨今、カイゼンは国内よりも海外で活発に取り組まれています。海外では「KAIZEN」と表記され、世界中の企業がトヨタ生産方式を研究しているのです。例えば、2015年1月にシンガポールにある航空機の修理拠点を訪れた際、現場には「カイゼ~ン」という声が響き、作業現場のさまざまな場所に「KAIZEN」という言葉が掲示されている光景を目の当たりにして衝撃を受けました。
こうした海外の取り組みに刺激を受け、私たちも本格的にカイゼンに取り組もうと動き始めました。そして2016年4月、整備部門で導入を開始し、1年後には全社的な展開へと発展させました。
──なぜ、非製造業であるANAがカイゼンの導入に至ったのでしょうか。
川原 カイゼンは元々、自動車の製造ラインを効率化するために考案されたものなので、一般的には製造業の取り組みとして捉えられています。当初、私たちも「製造業ではなく、製造ラインも持たないANAにカイゼンを導入して効果が出るのだろうか」と心配していました。
しかし、カイゼンについて学びを深めていくと、その本質は「いかに仕事の効率を良くするか」という点にあると気付いたのです。そのように考えると、製造業・非製造業といった区分は関係ありません。こうした視点を踏まえて「いかに効率良く仕事をできるか」ということを軸にカイゼンを捉え直し、導入を始めました。