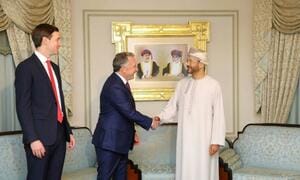太平洋上で「SM-3」を発射した米駆逐艦「ホッパー」(米海軍のサイトより)
太平洋上で「SM-3」を発射した米駆逐艦「ホッパー」(米海軍のサイトより)
ここ数年、ロシアと中国、そして北朝鮮も極超音速滑空弾(HGV:hypersonic glide vehicle)の開発・導入を推進している。
ロシアは、極超音速滑空弾「アバンガルド」を2019年12月に実戦配備したと報じられている。
アバンガルドは「R-36」、「RS-28」などの重ICBM(破壊力、すなわち発射重量または投射重量が大きいICBM=大陸間弾道ミサイル)に搭載して発射される。
中国は、極超音速滑空弾「DF-ZF」を搭載した「DF-17」(中距離弾道ミサイル)を2019年に実戦配備したと報じられている。
DF-17はDF-ZFを搭載するために開発された弾道ミサイルの一種である。DF-17の射程は1800~2500キロである。
DF-ZFは、多様な弾道ミサイルに搭載できるとされる。
北朝鮮は、2024年4月2日、 極超音速滑空弾を搭載した「火星16型」中距離弾道ミサイルの初めての発射実験に成功したと発表した。
実験では、分離された弾頭が予定どおりの変則軌道で飛行し、1000キロ先の日本海に正確に着弾したとしている。
また、北朝鮮は2025年1月6日、新型の極超音速弾道ミサイル発射実験(筆者注:新型がHGVのことか、または弾道ミサイルのことかは不明、あるいは中国のDF-17のようにHGVと一体なっている新型の弾道ミサイルの可能性もある)を行い、成功したと発表した。
発射実験では、弾頭が音速の12倍に達する速度で、予定された軌道に沿って1500キロ飛行し、公海上の目標水域に着弾したとしている。
金正恩総書記は「いかなる防御の障壁も突破し、相手に甚大な軍事的な打撃を与えることができる」と強調した。
上記のように我が国に友好的でない近隣の国々が、現有のミサイル防衛システムを突破できるとされるHGVの開発・導入を進めており、安全保障上大きな脅威となっている。HGVへの対処能力の構築が急がれる。
HGVの対処には、HGVを探知・追尾する手段と、HGVを撃破する手段が必要である。
日本政府は、HGVを探知・追尾する手段として、多数の小型衛星を一体的に運用して情報収集する「衛星コンステレーション」の整備費用として、2025年予算案に2832億円を計上した(出典:財務省「令和7年度防衛関係予算のポイント令和6年12月」)。
また、政府は2023年8月に、滑空段階迎撃ミサイル(Glide Phase Interceptor=GPI)を日米で共同開発することを決定した(出典:防衛省プレスリリース2023年8月19日)。
GPIは、その名前の通り、HGVを滑空段階で迎撃するミサイルである。
本稿では、日本のHGVに対する対処能力の構築の状況について述べてみたい。
以下、初めにHGVの特徴について述べ、次に日本の衛星コンステレーションの構築について述べ、最後に滑空段階迎撃ミサイル(GPI)の日米共同開発について述べる。