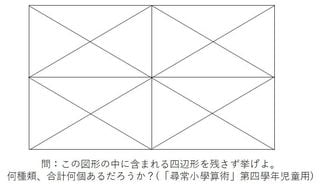大正時代の潮干狩り風景(写真:渡辺広史/アフロ)
大正時代の潮干狩り風景(写真:渡辺広史/アフロ)
(真山 知幸:著述家)
少子化がとどまることなく、私たちは深刻な高齢社会に直面している。子どもの数が減れば、深刻な労働力不足をもたらすばかりか、人口全体の減少によって、経済社会は活気を失っていく。また高齢層の割合が増えることで、年金制度は破綻に近づき、医療保険や介護保険などの社会保障費が増大していく。
少子化は、日本が抱える最も大きな社会問題といってよいだろう。少子化に悩まずに済んだ時代がうらやましくなるが、かつて大正時代の日本はむしろ「多子化」に苦しめられていた。
多子化に悩んで「間引き」も
令和3年に生まれた日本人の子どもは81万1604人。これは、データがある明治22年以降では最少の数である。これで6年連続の減少となり、少子化に歯止めがかからない。そんな今の日本から想像しにくいが、大正時代においては、むしろ「多子化」に悩まされていた。
大正時代の前半には、年間約180万人もの子どもが誕生している。「ベビーブーム」と呼ばれる昭和22年の約270万人に比べると、それほど多くないようにも思えるが、大正時代の総人口は、現在の半分にも満たない。
しかも、届出がないケースが現在よりも多かったことを考えると、実態は数字以上だといえるだろう。人口1000人あたりの普通出生率を見れば、大正9年の36.2をピークに、それ以降は下がる一方である。
大正時代、既婚者の女性は5~6回妊娠するのが当たり前で、なかには10回以上出産する女性も決して珍しくなかった。しかも、当時は病院ではなく自宅で産むのが一般的で、死産も年間に十数万件あった。にもかかわらず、それだけ多くの子どもが生まれているのは、妊娠回数が著しく多かったということである。
多子化で困るのは、やはり家計が圧迫されることだ。経済的な事情で、妊娠中絶の費用すらない場合は、生まれた後に窒息させて殺すといった「間引き」も行われていた。間引きは主に農村で行われており、それも労働力としての価値が低い、女児が多かったと言われている。