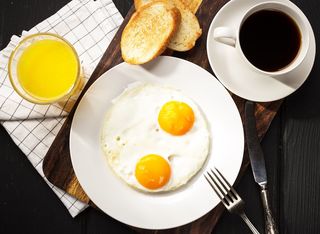車内販売サービスが縮小されるなど、乗りものにおける「食」の事情は転機を迎えている。
車内販売サービスが縮小されるなど、乗りものにおける「食」の事情は転機を迎えている。
お盆休み、帰省や旅行をするとき、乗りもので「道中食」をとる人もいるだろう。車内販売で買う弁当や、機内で出される料理・飲みものに心が弾む。
こうした道中食のあり方も、経済の仕組みに基づく。交通手段の高速化などを背景に、これらの食を乗りもの内で手に入れる必然性は薄れてきた。食堂車や車内販売、それに機内食などの歴史から感じられるのは、これら道中食の「実用性」が確実に減ったということだ。
日本初の食堂車・車内販売は19世紀末ごろ
鉄道車内や航空機内での「食」は、いつ始まったのか。
鉄道については1868年、米国の実業家ジョージ・プルマンがシカゴ・ノースウェスタン鉄道に食堂車を導入したのが世界初の食堂車とされる。当時、すでに長距離鉄道が走り、駅間も長かった米国では、「必要な品は車内で手に入れるもの」という風潮が乗客にあったようだ。船旅文化の影響もあったろう。
日本では、1899(明治32)年5月、山陽鉄道が現在のJR線にあたる京都-三田尻(現・防府)間の急行で食堂車を導入したのが初とされる。メニューは、「西洋料理」が一等、二等、三等の3段階、また酒類は「正宗」「アサヒ」「キリン」「サッポロ」のほか葡萄酒やウイスキーも揃えていた。山陽鉄道は当時、瀬戸内航路との汽船との競争の真っただ中。とりわけ旅客サービスに心血を注いだという。
これと別に、2年前の1897(明治30)年には、東京で牛肉缶詰製造業の中川幸七や実業家・政治家の伴直之助らが「乗客用達株式会社」を起こす動きを見せていた。朝日新聞の同年9月9日付によると、彼らは上等車と中等車の間に、食品や料理を給仕する車両を連接することを企て、鉄道局などと折衝していたようだ。日の目を見なかったのだろうか。