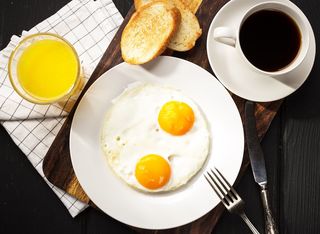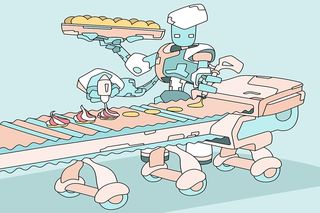ウリ科のゴーヤー。果皮に苦味があるため「苦瓜(ニガウリ)」とも。他に「蔓茘枝(ツルレイシ)」の和名も。
ウリ科のゴーヤー。果皮に苦味があるため「苦瓜(ニガウリ)」とも。他に「蔓茘枝(ツルレイシ)」の和名も。
人間は、他の動物と違って、食べものの「苦味」を味わってきた。日本人も例外ではない。たとえば、山菜や菜花などを口にしては、甘味や旨味の中に感じられるほろ苦さを「大人の味」などと嗜好してきた。
とりわけ「苦味が風味の中心」と感じられるような食材もある。真っ先に思いつくのが「ゴーヤー」だ。もちろん他の味覚成分も入っているだろうが、たいていの人はゴーヤーから苦味を思い浮かべるのではないか。そして食べてみるとやっぱり苦い。このゴーヤーの苦さを苦手とする人がいる一方で、ゴーヤーの苦さにハマる人もいる。あの苦味が何かしらの“力”を持っているのは確かだろう。
今回は、旬も迎えた苦い食材「ゴーヤー」に光を当てたい。前篇では、日本におけるゴーヤーの歩みを辿っていきたい。長らく地方野菜でありつづけたゴーヤーが、都市の人びとをも取り込んで全国的な野菜になった経緯を追う。ここでもやはり「苦味」が鍵となる。
後篇では、ゴーヤーを対象としている日本での研究について伝えたい。最近の研究によって、この植物の中で苦味がどうつくられるのかが詳らかになってきた。人とゴーヤーの新たな関係性を探るべく、研究者に話を聞く。
17世紀以降の書物に「苦瓜」が登場
「ゴーヤー」は産地である沖縄での言葉だ。その語源は、中国語の「苦瓜(クーグア)」からという説、あるいは英語で「ヒョウタン」を意味する「Gourd(ゴード)」からという説もあり、諸説紛々だ。
一般的に「苦瓜(ニガウリ)」ともよばれる。中国でも「苦瓜」と称されてきたことの影響によるものだろう。また「蔓茘枝(ツルレイシ)」という植物名もある。こちらは、ライチとして知られる「茘枝(レイシ)」の実に喩えたものではないかとされる。
語源からも分かるように、ゴーヤーは日本に伝わってきた植物だ。原産地は東南アジアからインドにかけての「熱帯アジア」とされ、日本には中国から入ってきたとみられる。