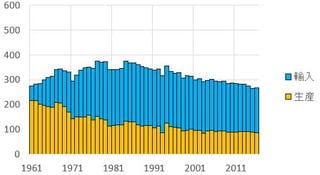「城山に登って南洲翁を思う。西南戦争の最後の戦いの場となった城山に後日、登って読まれた詩のようですね。麒閣(きかく)とは漢の武帝の宮殿、つまり明治新政府の喩(たと)えです。そこに集う賢人は大勢いるが、西郷は頭一つ抜きんでていた。その人の為した功績を誰がよじ登ることができようか、城山は今も深い緑に覆われている」
2つ目の詩の解説が続く。
「火車つまり列車が、かつて激戦の地となった山の麓を過ぎていく。弾丸が飛び交い硝煙(しょうえん)の香りに満ちた西南戦争の日々を私は思い出す。西郷は身まかって久しいが、薩摩健児の心意気を誰が伝えていくのだろうか・・・」
そこで古島が話を引き取った。
「最後の下りは、もっと意味深長だよ。西郷の心意気を継ぐのは他でもない、この自分だという反語だろう。これを詠んだのは昭和5年、もう間もなく総理大臣の椅子に手が届きそうな時だからな、犬養木堂の気迫たるや尋常じゃないよ」
「話せば分かる」には、別の意味がある
誰ともなくつぶやいた。
「話せば分かる、か・・・」
犬養毅はその時、ピストルを突きつける若い軍人に対峙(たいじ)し、「話せば分かる」と説いた。軍人は「問答無用」と銃弾を放った。「話せば分かる」は、生粋の政党政治家らしい最期の言葉だというのは、誰もが知る有名な話だ。
「違う違う、それは違う」
突然、古島が身を乗り出した。思わぬ反応に、皆の怪訝(けげん)そうな視線が集まる。
「話せば分かるなどと、木堂は、そんな単純な言葉を発する男ではないよ」
古島が瘦せこけた頰を赤らめると、アンカの周りが静まり返った。誰もが古島の言葉の真意を摑(つか)みきれないでいる。「話せば分かる」という言葉には、何か別の意味があるということか。
「時代が大きく動く時、政治家は誰もが己を試される。その流れに乗るのか、頰かむりで様子を見るのか、それとも濁流に立ち向かうのか」
古老の声が張り詰めてくる。