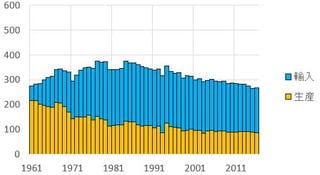名誉でも、金でもなく
古島の人生の出発点は、新聞記者だ。明治の四半世紀、「無冠の帝王」つまり一記者として生きたことが、この男にとって何よりの誇りである。かつて、新聞『日本』の編集長として活躍し、正岡子規(まさおかしき)を世に出した。『萬朝報』では政治記者として、マムシと呼ばれた黒岩涙香(くろいわるいこう)と特ダネを連発。
現役を退いてからは毎日新聞社の客員となり、文字通り毎日、新聞社に通った。同時期の客員、新渡戸稲造(にとべいなぞう)や竹越与三郎(たけごしよさぶろう)が首脳部の個室に閉じこもるのとは対照的に、古島はいつも編集室の一角に陣取った。そこで政治部や論説室の悪童どもに取り囲まれて談論風発、いざ政局が動けば鋭く先を読んだ。
緒方竹虎(おがたたけとら)や岩淵辰雄(いわぶちたつお)ら若手の記者や文化人たちは「古島財閥王をかこむ会」を結成、必ず月に一度、寄り合うようになった。「かこむ会」には、こんな笑えぬ話がある。会費が1人10円ほどだった時代、一度だけ古島が気前よくポンと100円札を出した。何があったか「釣りは要らぬ」などと似合わぬ言葉を吐いた。だが貧者の一灯はあまりに痛々しく、誰もその金にふれることができなかったという。
そんな武骨一辺倒の男が、戦前、記者から政治家に転身したのには理由があった。記者生活を謳歌していた古島が政界に飛び込んだのは、名誉のためでも、金のためでもない。それは、ある男に一生を捧げるための決断だった。
米寿の祝いの席で
1952(昭和27)年4月5日。サンフランシスコ講和条約の発効を3週間後に控えたこの日、横浜杉田にある実業家西幸太郎(にしこうたろう)の別荘で、数えで88歳を迎えた古島の米寿の祝いが開かれた。
「いったい誰が宣伝した、こんな祝いの席はおよそ僕のガラではないよ」
次々に訪れる懐かしい顔に囲まれて、古島は照れくさそうに拗(す)ねている。西邸は、京浜急行の杉田駅からほぼ1キロ、坂を登り切った丘の上にある。眼下には磯子の浜辺、遠くに本牧の鼻が見え、その向こうには東京湾の海原が広がる。邸内の桜は今が盛りと咲き誇り、桜花爛漫の庭は米寿の祝いにこれ以上ない借景を作っている。