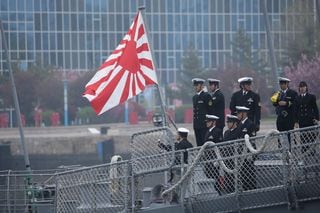加えて、2020年の「発送電分離」に合わせ、英国のように低炭素化に関する政府との契約(CfD=変形固定価格買取制度)ルールを設けるなど、原発を低炭素電源に位置付けながら新増設を促す環境を整備することも急務だ。
2015年のCOP21で採択された「パリ協定」により、長期目標として気温上昇を1.5~2.0度に抑えるために、各国が自国の目標を定め、5年毎に条約事務局に提出・更新し、その進捗状況を2年に1度レビューすることとしている。日本もこれを遵守しなければならないことを忘れてはならない。
次に考えなくてはならないのは、もっと長期的に腰を据えてやらねばならない対応だ。国のエネルギー政策は、50~100年先を見越しながら、10~20年先までの具体策を提起していくのが望ましい。日本では過去、原子力委員会が「原子力長期計画」を5年毎に改定し、長期にわたるかつ多くの叡智を投入した検討を重ねて、核燃料サイクルの確立や「プルトニウムは国産資源」という政策論を定着させてきた(今の原子力委は、原子力長期計画の作成をしていない)。
原発で使ったウラン燃料の中には、核分裂していないウランや原子炉内で生まれたプルトニウムが含まれている。その使用済み核燃料からはウランやプルトニウムを取り出すこと(再処理)により、燃料として再利用(リサイクル)できる。
この核燃料サイクルを繰り返すことにより、ウラン資源は約100倍利用可能となるわけだ。取り出されたプルトニウムは、再処理技術が生み出した「国産資源」となり、エネルギー資源に乏しい日本にとっては貴重なエネルギー源となる。地球規模での人口増やエネルギー消費増により、近い将来、化石燃料やウラン資源の争奪戦が始まる可能性がある。核燃料サイクルの確立は、日本のエネルギー安全保障にとって、まさに要となる。
プルトニウムについては、1982年に「常陽」で、1988年には「ふげん」で、小規模ではあるがリサイクルした実績がある。だが1F事故以降、再エネ礼讃一辺倒のマスコミや、原子力推進に躊躇している政治・行政の姿勢もあって、日本のエネルギー政策は短絡的転換が図られ、長期的な見通しが立てられないものとなっている。
その結末が、核燃料サイクルの柱の一つ「もんじゅ」の廃炉だ。さらに再処理を担う六ヶ所再処理工場は、竣工の許可を取得する寸前になっているものの、原子力規制委の“牛歩審査“に嵌っている。こうした状況が長引くと、せっかく整えて来たプルトニウム利用の技術基盤・インフラが廃れてしまう。
高速増殖原型炉「もんじゅ(Monju)」(福井県敦賀市、2008年12月24日撮影)。(c)AFP/Harumi OZAWA 〔AFPBB News〕
現に、高速炉の研究開発現場やMOX燃料製造現場がなくなろうとしているのだ。JAEA(日本原子力研究開発機構)や、原子炉メーカーのプルトニウム利用に係る若手技術者の数は加速度的に低下してきている。長期にわたって発注実績がないことで、ウラン燃料やMOX燃料に係る技術の空洞化が危惧されている。高速炉について日本は、フランスのASTRIDを活用することとしていたが、報道によればASTRIDは予算制約から事実上断念されるようだ。つまり、フランスに依存する高速炉開発は破綻を来たしているのだ。
もんじゅは国際的管理下で再活用すべき
一方、日本が開発を進めてきた「もんじゅ」は、2018年に廃炉が決定されているが、これは技術的問題がある原子炉ではないので、このまま解体するのはあまりにももったいない。ある閣僚経験者は「運のない原子炉だ」と語るが、もう一度魂を入れて開発・運営を管理する体制を整備し、これまでの建設資金約6000憶円・累積投資額約1兆円を有効活用することを模索すべきではないだろうか。