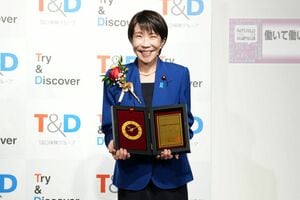豊穣な「体験」こそが人工知能に打ち勝つ力
文学を通じた「疑似体験」は人生拡張の手段
篠原 信
農業研究者
2019.1.24(木)
ここからは、JBpress Premium 限定です。
カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら
次の記事へ
日本人が取り戻すべき「人の力を引き出す“力”」
ここからは、JBpress Premium 限定です。
カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら