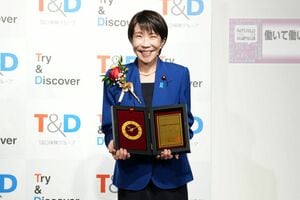文学を通じて得た「体験」は、きっと大きな財産となる。
文学を通じて得た「体験」は、きっと大きな財産となる。
(篠原 信:農業研究者)
その子は、全教科満点を取るような、成績優秀な小学生だった。ある日、理科の実験で「天秤はかりで塩を10g計り取ってください」と指示されたとき、その子は迷いなく「10g」と書いた紙を片方の皿に載せて、もう片方の皿で塩を計ろうとした。
「そんな子がいたので衝撃を受けた」と、その先生は言った。私は聞いただけで直接その子を見たわけではないが、座学ばかりしているとそういうことになるかも、と思ったことをよく覚えている。
大学生になると、教養を身につけようと心理学を学ぶ学生が多い。私はそうした相談を受けると「小説は読むほう?」と尋ねることにしている。ほとんど読んだことがない、という答えで、本人が不器用なタチだったら、「心理学に手を出すのは、当面やめておいたほうがいい。頭でっかちになってしまって、かえって人の心が見えなくなるから」と伝えることにしている。
小説などの文学作品は、「別の人格・人生を疑似体験」できる、すばらしいシミュレーションゲームだと言ってよい。気弱な人間も、粗暴な人間も、繊細な人間も、優しい人間も、さまざまな人格になりきって、それぞれの場面で自分ならどうするだろう? ということをハラハラしながら考える、すばらしい疑似体験を、いくらでも積むことができる。
できの悪い小説は、「それはないやろう!」とツッコミたくなるような展開が多い。「いやいや、主人公が次の場面でそんな行動なんて、ありえない! もしそうなら、さっき発言していたのは何やってん!」と、もう、クソミソに非難したくなる。
ところが、歴史の風雪を乗り越えてきた文学作品は、そうした不自然さがまるでない。カミュの「異邦人」は、「太陽がまぶしかったから」殺人したという、要約だけ聞けば「オイオイ」と突っ込みたくなるような、荒唐無稽な展開だが、小説を読んでみると、無理がない。そんなこともあるのかもしれない、と思ってしまう。
なぜか。人の心理を巧みに描写しているからだ。そしてその心理の流れが、非常に自然に感じられるからだ。