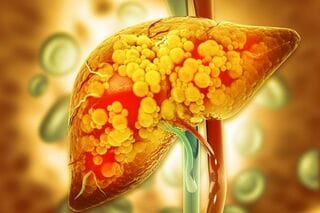「論憲」では曖昧すぎて有権者は選択できない
これまで野党、特に旧立憲民主党の流れを汲む勢力といえば、強固な「護憲」の立場にあるというイメージが世間一般には流布していたからだ。しかし、この「驚き」は、実のところ過去の経緯を詳細に振り返れば、必ずしも当を得たものではないことがわかる。
むしろ、中道改革連合、そしてその前身である立憲民主党や民主党の歴史を紐解けば、彼らが一枚岩の護憲政党であったことはなかった。小川氏の発言は唐突な変節などではなく、ある種の「党の体質」や「伏流していた思想」が表面化したに過ぎないという側面が見えてくる。
そもそも、鳩山由紀夫元首相は「創憲」、すなわち新しい憲法を創るという立場を標榜していた。これは現状の憲法を維持する「護憲」ではなく、憲法を変える、あるいは作り直すという「改憲」のバリエーションの一つである。
また、立憲民主党の創設者である枝野幸男氏も、かつて民主党政権時代に雑誌(『文藝春秋』)に憲法改正案の私案を公表した過去がある(後に撤回を宣言)。
これらの事実は、野党第一党の系譜において、憲法改正をタブー視せず、むしろ積極的に関与しようとする姿勢が脈々と受け継がれてきたことの証左である。したがって、小川新代表が改憲議論に前向きな姿勢を示したこと自体は、党の歴史的文脈から見れば決してそれほど特異なことではない。
さらに、小川氏の姿勢を理解する上で重要な補助線となるのが、旧立憲民主党内に存在した中堅・若手議員によるグループ「直諫の会」(ちょっかんのかい)の存在である。中谷一馬氏や青柳陽一郎氏、塩村あやか氏らが名を連ねたこのグループは、2023年に書籍(『どうする、野党!? 「大きな政治」と「新しい改革」で、永田町の常識を喝破!』(幻冬舎))を取りまとめ、その中で「論憲」という立場を明確に打ち出している。
同書によれば、「護憲か改憲か」という二項対立的な問い設定自体がすでに古く、時代遅れであるとする。その上で憲法について積極的に論じていく「論憲」の立場をとる、と宣言した。
小川新代表の一連の発言は、まさにこの「直諫の会」が提唱してきた「論憲」のロジックと軌を同じくするものであり、その潮流が中道代表の見解として前面に出てきたと解釈することができそうだ。
この「護憲か改憲かという二元論は古い」「これからは論憲だ」という主張は、一見すると理知的で、建設的なスタンスのように響くかもしれない。
長年のイデオロギー対立を乗り越え、実務的な議論を進めようとする姿勢は、無党派層や中道層へのアピールとして一定の効力を持つ可能性もある。
しかし、現在の、そしてこれからの厳しい政治情勢において、この「論憲」という立場は、野党第一党が取るべき戦略として本当に有効かつ適切であろうか。これには強い疑義を呈さざるを得ない。
なぜなら、「憲法について議論する」ということ自体は、戦後80年にわたって、日本社会において絶え間なく続けられてきた営みそのものだからである。
ある意味、日本社会は憲法を「論憲」し続けてきているだけに、その意味では現状踏襲にすぎない。
他方で、国会の憲法審査会において、あるいはメディアやアカデミズムの世界において、憲法に関する議論が国民に理解できるかたちで尽くされたことはないと言っても過言ではないだろう。国民の憲法理解が急速に進んだというニュースは管見の限り近年見つけることはできないからだ。
80年もの長きにわたり議論を積み重ねてきただけに、政治に求められているのは「議論をすること」そのものではなく、その議論の果てに「どのような結論を導き出すのか」、つまり当面護憲を採るのか、それとも改憲を採るのか明確にする決断であろう。
特に選挙という、有権者が政治的な意思表示を行う最大の機会において、政党が曖昧な態度を取り続けることは、有権者の選択の機会を奪うことに等しい。
「護憲か改憲か」という図式は、確かに単純化されすぎたきらいはあるものの、政治的立場を識別するためのリトマス試験紙として、依然として有効なのではないか。
憲法を変える必要があると考えるならば「改憲」、当面はその必要がない、あるいは現在の改正案には反対であると考えるならば「護憲」。このどちらかの旗幟を鮮明にすることによって初めて、有権者は自らの憲法を巡る価値観に合致する政党を選ぶことができるはずだ。