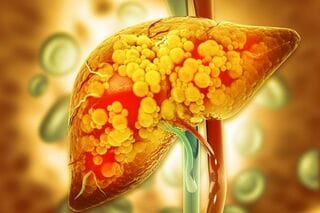イラン革命から47年を迎えた2月11日、首都テヘランで式典が行われた。写真は式典で演説するペゼシュキアーン大統領(写真:新華社/アフロ)
イラン革命から47年を迎えた2月11日、首都テヘランで式典が行われた。写真は式典で演説するペゼシュキアーン大統領(写真:新華社/アフロ)
イラン情勢が緊迫度を増している。昨年12月末に発生した大規模な反体制デモでは多数の国民が命を落とした。米国との核協議の行方によっては、トランプ大統領が武力行使を決断する可能性も捨てきれない。極度のインフレによる生活苦などが伝えられる中、いまイラン人がどのような状況に置かれているのか、攻撃姿勢を崩さない米国に対してどんな思いを抱いているのか——。長年現地に滞在し、『イランの地下世界』(角川新書)の著書もある若宮總氏が、そのリアルな姿をレポートする(JBpress編集部)。
「自国民に対する虐殺としては人類史に残る規模だ」
「ショックと悲しみ、そしてもの凄い怒りが、この国を覆っている」
2026年1月半ば、約20日間にわたり続いた大規模な反体制デモが鎮圧された直後、友人で30代のアリ君(仮名、以下同様)が私にくれたメッセージアプリ「テレグラム」での言葉だ。
デモの激化にともない、当時イランのインターネットは当局によりほぼ完全に遮断されていたが、2〜3時間に数分だけ、奇跡的に接続が可能になる瞬間があった。そこを狙ってアリ君は、途切れ途切れでも諦めることなく、日本で暮らす私の元にイランの「今」を伝えようとしていた。
ショック、悲しみ、怒り——。
それらは、あの日からひと月以上たった今も、まったく癒されていない。
デモの弾圧により殺害された人の数は正確には不明だが、少なくとも7000人以上、多く見積もって3万人といわれ、6万人という衝撃的な数字も出てきている。
ちなみに、イラン当局の公式発表では3117人で、その大半は「外国の手先により殺害された」ということだが、今さらそんな官製デマを鵜呑みにするのは体制派の御仁くらいだろう。仮に7000人規模だとしても、「自国民に対する虐殺としては人類史に残る規模だ」とイラン人は口を揃える。
イランの“イスラム”体制は、その腐りきった体制を存続させることが自己目的化しており、そのためとあらば自国民の命さえ平気で奪いにかかってくることくらい、イラン人なら子供でも知っていたはずである。