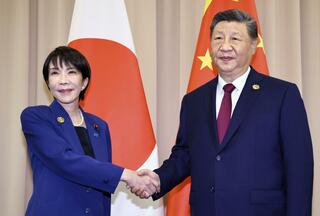「敵」に対して寛容だった初期の清朝
1616年、満州の諸部族を統一したヌルハチは、後金を建国した。その子ホンタイジは1636年に皇帝に即位し、国名を大清帝国に改めた。1644年には北京に首都を移
残り2266文字
1616年、満州の諸部族を統一したヌルハチは、後金を建国した。その子ホンタイジは1636年に皇帝に即位し、国名を大清帝国に改めた。1644年には北京に首都を移
残り2266文字
ここからは、JBpress Premium 限定です。
カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら