万博で「三輪立ち乗り」の消防巡回も!海外展開と株式上場を目指すホンダ発スタートアップ「ストリーモ」の実力
2025.6.17(火)
ここからは、JBpress Premium 限定です。
カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら
あわせてお読みください
本日の新着

なぜ大相撲だけが視聴率20%を取れるのか?WBC・W杯以外は苦戦する地上波スポーツ中継で相撲が勝つ構造的強さ
チケットは全日程完売、視聴率は週間上位独占、インバウンド頼みではない令和の大相撲が熱い理由
長山 聡

【原油ウォッチ】米国のベネズエラ攻撃、イラン大規模デモ…地政学リスク急上昇でも原油60ドル台を回復しない理由
藤 和彦

“政冷経熱”モードを強める欧米関係、傍若無人なトランプ政権が進めるウクライナ和平協議はもはや機能不全
【土田陽介のユーラシアモニター】大統領のグリーンランド領有発言に怒り心頭、“政冷経冷”に移行する日も近いか
土田 陽介

なぜ古代日本では遷都が繰り返されたのに、平安京で終わったのか?古代日本の宮殿と遷都が映し出す権力と政治
【著者が語る】『宮殿の古代史』の海野聡氏が語る、宮殿から見る日本史の奥深さ
関 瑶子
自動車の今と未来 バックナンバー
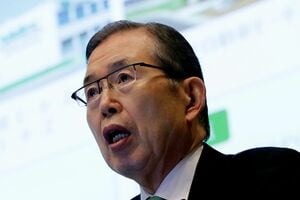
ニデックにアクティビストの影、ガバナンス不全で永守氏の院政も…“イエスマン”の社外取では「第2の創業」は遠い
井上 久男

【試乗レポート】スバル新型「フォレスター」で1400km!ストロングハイブリッド、ガシガシ系を卒業した6代目の実力
桃田 健史

【2026年の自動車業界】破談から1年、日産とホンダは再統合へ向かうのか──技術提携だけでは埋まらない課題
井元 康一郎

【2026年の自動車産業】中国に負ける日本、ハード・ソフトで圧倒的な差も…現実を直視し技術を「盗み返す」べき理由
井上 久男

日本で販売減のボルボ、だが改良版「XC60」1200km試乗で見えた“静かなプレミアム”路線の強み
井元 康一郎

川崎市が挑む「モビリティハブ」、静かに進む都会の「陸の孤島化」の救世主になるか?
桃田 健史








