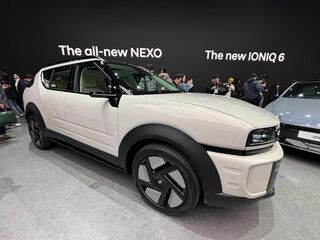日本で最も売れているバッテリーEVの日産「サクラ」(写真手前)。軽自動車乗り比べ一般試乗会にて(写真:筆者撮影)
日本で最も売れているバッテリーEVの日産「サクラ」(写真手前)。軽自動車乗り比べ一般試乗会にて(写真:筆者撮影)
(桃田 健史:自動車ジャーナリスト)
最近、世界市場でEV普及の速度が鈍化しており、これを「EVは踊り場」と表現することが多い。だが、その出口はまだ見えてこない。
例えば、トヨタ自動車の状況を見てみよう。5月8日に発表した2026年3月期の業績見通しでは、トヨタ・レクサス販売の電動化率を49.8%とした。台数で518万4000台。
このうち、最も多いのがHEV(ハイブリッド車)で2025年3月期と比べて109.2%の466万3000台、次いでPHEV(プラグインハイブリッド車)が同105.0%の20万9000台、バッテリーEV(電気自動車)は213.8%の31万台、そしてFCEV(燃料電池車)は前期と同等で1万台にとどまる。
バッテリーEVは大きく伸びると予想しているものの、トヨタの当初の「めど」と比べるとほど遠い。
時計の針を少し戻すと、豊田章男会長(当時社長)は2021年12月14日、いまはなき東京お台場の自動車関連施設MEGA WEBで「バッテリーEV戦略に関する説明会」を実施した。その中で「2030年までにすべてのカテゴリーでバッテリーEVのフルラインアップを実現し、欧州、北米、中国でバッテリーEV100%、グローバルで100万台の販売を目指す」と公表した。さらにその先、2035年にグローバルでバッテリーEV100%を掲げた。
合わせて、大型ピックアップトラック、中小型SUV、商用車、そして超小型車まで、その時点ですでに販売されていた「bZ4X」を含めて合計16ものコンセプトモデルを一気に公開したことに集まったメディアは驚いた。
こうした、何年までに何万台という数字を、トヨタでは「基準」と呼ぶ。中期経営計画や通期見通しでの達成目標ではなく、サプライヤーなどと事業の将来イメージを共有するための数字という解釈である。
その基準を、トヨタはこれまで段階的に見直してきたが、今回の会見で佐藤恒治社長は「市場の実需を重視する」として、2026年にバッテリーEV100万台という数字を事実上、軌道修正した。
その上で、「エネルギーの未来を見据え、多様な選択肢でカーボンニュートラルを目指す」という、マルチパスウェイという従来の考え方を堅持すると説明する。