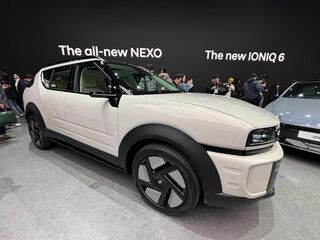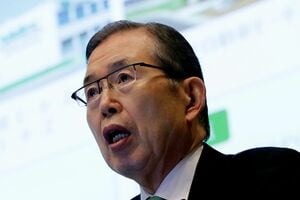自動車各社が相次ぎEV戦略を見直し
マルチパスウェイとは、ハイブリッド車、プラグインハイブリッド車、バッテリーEV、燃料電池車に加えて、ガソリン車やディーゼル車のエンジン小型化やカーボンニュート
残り2754文字
マルチパスウェイとは、ハイブリッド車、プラグインハイブリッド車、バッテリーEV、燃料電池車に加えて、ガソリン車やディーゼル車のエンジン小型化やカーボンニュート
残り2754文字
ここからは、JBpress Premium 限定です。
カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら