戸籍にフリガナ記載、なぜこれが革命的に重要なのか?終わらない行政DXの迷宮を抜ける最適解はフリガナ
暗黒の世界に行政を閉じ込めてきた「文字の呪い」、乱立する文字コードや外字に悩まされることもなくなる?
2025.6.18(水)
ここからは、JBpress Premium 限定です。
カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら
あわせてお読みください

デジタル庁が発足して1年、ちっとも進まないデジタル化の根源に横たわる呪い
個人を特定するIDを秘匿すべきものと考える限り、デジタル先進国にはなれず
榎並 利博

デジタル化のメリットが反映されていないマイナンバー制度の致命的欠陥
「番号は危険」という非科学的感情が作り出す「空気」と、それを恐れる政治
榎並 利博
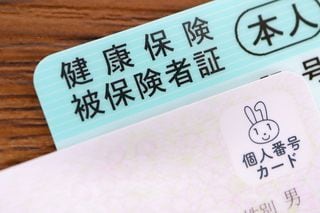
マイナンバーカードと健康保険証の一体化、今のままでは大惨事が起きかねない
電子証明書を本人確認で使うのは危険、デジタル社会ではなぜ番号が必要なのか
榎並 利博

日本をデジタル後進国たらしめている根源、マイナンバーの呪いを解く呪文とは
マイナンバーは氏名や住所と同じ、制度を再構築して正々堂々と使おう
榎並 利博

マイナンバー賛成・反対の不毛な問い、日本のデジタル化を阻む「呪い」の正体
自由権と社会権の間で揺れ動く番号制度、やるべきはデジタルを使った国の監視
榎並 利博
本日の新着

かつて「野球弱小県」ながら野球熱の高かった新潟県、今は子どもの未来を第一に県球界一丸で取り組む「先進県」に
広尾 晃

「連休で仕事が休みになっちゃって。3000円くらい貸してもらえませんか」大型連休で干からびる派遣高齢者の日常
【令和版おじさんの副業NEO】所持金500円の派遣高齢者が大型連休を乗り切った方法(前編)【JBpressセレクション】
若月 澪子

歯の治療費250万、孫へ贈与が500万…退職金が「蒸発」し、年金が「枯渇」する恐怖
「そこそこの貯蓄」があっても安心できない、年金生活者を襲う想定外の出費
森田 聡子

高市首相の“安倍流”電撃解散案の衝撃、大義は「積極財政」の是非か、党内制圧と国民民主連立入りで狙う盤石の権力
身内も欺く「最強の不意打ち解散」へ、自民党単独過半数の獲得が焦点
市ノ瀬 雅人
日本再生 バックナンバー

「連休で仕事が休みになっちゃって。3000円くらい貸してもらえませんか」大型連休で干からびる派遣高齢者の日常
若月 澪子

いまさら?軍民両用物資の対日輸出規制、何が該当するかは中国当局が判断、品目リストの明示なく超絶イライラ
山本 一郎

「墓じまい」と「家じまい」に踏み切った徳川慶喜家、歴史上の著名人の墓が墓じまいされるのはなぜか?
鵜飼 秀徳

「地震リスクが世界一大きい」とされる浜岡原発のデータ不正、危険な原発を「安全」にすり替える悪質な体質
添田 孝史

気象庁・元地震火山部長が東電裁判の裁判官に憤慨、「科学に向き合わないその態度はまるでガリレオ裁判の裁判官」
添田 孝史

加害者が被害者を罵倒することも、事件の被害者や遺族が刑務所にいる加害者と言葉を交わそうと思うのはなぜか?
長野 光 | 藤井 誠二



