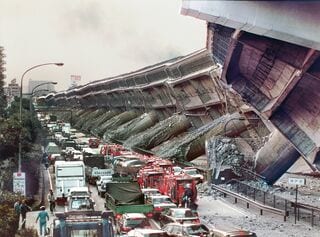能登半島地震で支援物資の拠点となった石川県珠洲市の体育館=2024年1月16日撮影(写真:共同通信社)
能登半島地震で支援物資の拠点となった石川県珠洲市の体育館=2024年1月16日撮影(写真:共同通信社)
災害時に使用する政府の支援物資の備蓄拠点が、次第に整備されてきました。現在は東京都立川市の1カ所だけですが、これを2025年度中に合わせて計8カ所に拡大。地域の要望を聞き取る前に政府の判断で緊急物資を現地に送り込むプッシュ型支援の拠点となります。災害大国の日本にあって、これまで政府が支援物資を備蓄していなかったことも驚きかもしれません。政府の「災害支援物資備蓄拠点」とは、どのような役割を負っているのでしょうか。やさしく解説します。
東京拠点に加え新たに7カ所
内閣府の防災担当大臣である坂井学氏は今年2月28日の定例会見で、災害支援物資の備蓄拠点が一部決定したことを明らかにし、次のように述べました。
「大規模災害では、国がプッシュ型支援を行うこととしておりまして、そのためには、その時により迅速に送るためには、分散をしておく、分散備蓄というのは大変重要なポイントだと思っております」
キーワードは「分散備蓄」です。災害はいつ、どこで起きるかわかりません。とくに大きな地震の事前予測は困難。備蓄拠点も国土に分散して整備しておかないと、備蓄拠点と被災地の距離が遠すぎて、「いざ」というときに必要物資を現地に輸送できない恐れがあります。
ところが、災害に備えた政府(内閣府)の物資備蓄は、実はまだ始まったばかり。備蓄拠点は現在、東京にしかなく、物資の備蓄が始まったのも2020年からです。まだ5年の歴史しかありません。日本では災害に備えた物資の備蓄は、主に都道府県や市区町村が担うことになっていたためです。
ただし、東日本大震災(2011年)をはじめ、熊本地震(2016年)、能登半島地震(2024年)などでは、自治体の対応には限界があることが改めて浮き彫りとなり、発災から遅くとも3日以内に必要物資を現地に届ける体制を整える姿勢を内閣府は打ち出していたのです。
内閣府の発表によると、関東地区をカバーする現在の東京拠点に加え、2025年度中に全国7カ所(北海道、東北、中部、近畿・中国、四国、九州、沖縄)で新たに備蓄拠点を整備する方針です。このうち、この2月末の時点では、北海道は札幌市、四国は高知県、九州は熊本県に拠点を設けることが確定しました。
現在稼働中の備蓄拠点は、東京都立川市の「立川広域防災基地」内に置かれています。この防災基地は、かつて旧日本軍の立川飛行場、戦後は米軍立川基地として使用されていた場所です。115ヘクタールという広大な敷地に自衛隊や海上保安庁、東京消防庁などの施設が整備され、首都圏などで大規模災害が起きた際、人命救助などに即応できる体制を整えています。
その一角にあるのが、内閣府と国土交通省の出先機関が陣取る「立川防災合同庁舎」です。発災時にはさまざまな連絡調整や指揮をここで行うことが想定されています。この建物に隣接する倉庫が政府の備蓄拠点になっているのです。