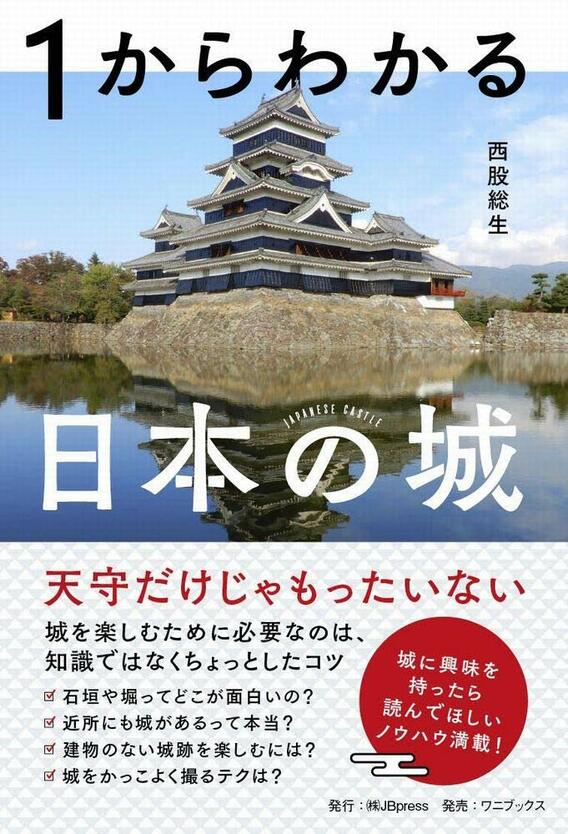京都御所 撮影/西股 総生(以下同)
京都御所 撮影/西股 総生(以下同)
(歴史ライター:西股 総生)
なぜ権力は自壊しないのか
筆者は本サイトに以前「歴史から考える権力が倒れる時」という記事を掲載した(7月23〜30日)。本稿は、その続編である。
前稿では日本史を俯瞰することから、権力というものは腐敗・弱体化しても決して自壊はせず、外から打撃が加えられて初めて倒壊する、という法則を導き出した。ここでいう「権力」とは、一定のエリア(地域や国)とそこに住む人民を支配する力のことであるが、では、なぜ権力は自壊しないのだろうか?
この問題を考えるヒントとして、既存の権力が打倒されずに新しい権力が成立し、両者がしばらく併存した事例を見てみよう。12世紀の末に源頼朝が打ち立てた武家政権=鎌倉幕府の場合である。
源頼朝の挙兵は、当初は地方の小さな叛乱にすぎなかった。しかし、多くの東国武士が参加した結果、東国独立運動の様相を帯び、最終的には武士による東国自治政権に落ち着いた。頼朝がこうした現実路線へと舵を切った最大の理由は、「支配システムをどう構築・確保するか」という命題に向き合った結果だ。
 石橋山古戦場跡。250騎の兵を率いて石橋山に進出した頼朝は討伐軍に蹴散らされた
石橋山古戦場跡。250騎の兵を率いて石橋山に進出した頼朝は討伐軍に蹴散らされた
「支配システム」というと、武士たちをどう従えるか、みたいな問題をイメージするかもしれない。でも、そんな抽象的・精神論的なことより、もっと大切な現実的問題がある。新政権の財政基盤をどうするか、である。
話は少々遡るが、日本に本格的な中央政権が誕生したのは概ね8世紀のこと、いわゆる律令国家である。この律令国家は中央集権体制、つまり唯一の中央政権が全国から一律基準で一元的に税を取り立てるシステムであった。
 川崎市の橘樹(たちばな)郡官衙遺跡。律令国家は国や郡ごとに官衙(役所)を置いた
川崎市の橘樹(たちばな)郡官衙遺跡。律令国家は国や郡ごとに官衙(役所)を置いた
ところが、権力の座にあった貴族たちは300年ほどかけて、律令国家の税制システムを少しずつ自分たちの利益になるように改変してゆき、ポストや職掌も利権化していった。
その結果、12世紀には「荘園公領制」というシステムが日本を支配するようになっていた。全国の土地と人民が産する富は、荘園と公領という二つのコースに分かれ、いくつもの中抜きをへて上へ上へと吸い上げられ、中央の貴族や院、大寺社へと集積される。
このシステムにおいては、年貢や租税を徴収し、取りまとめ、上級権力へと取り次ぐ職務などが、中抜き利権となる。荘園の年貢とは、もともとは公領における租税の名義を読み替えたようなものだから、「荘園公領制」というシステムとは、とどのつまりは徴税システムである。
12世紀末に東国の武士たちを率いて挙兵した頼朝は、敵から接収した荘園・公領の地頭に任ずる、という形で配下の武士たちに中抜き利権を与えた。さらに、自らが荘園領主や知行国主という上澄みを吸う地位を得ることで、将軍(鎌倉殿)の権力を確立した。おわかりだろうか。支配権力を現実的に担保するのは、徴税システムに他ならないのである。
 源頼朝は鎌倉に日本初の武家政権を打ち立てた
源頼朝は鎌倉に日本初の武家政権を打ち立てた
源頼朝は、朝廷を倒して「荘園公領制」という既存のシステムを破壊するのではなく、パラサイトすることによって政権を樹立した。そして、頼朝の下でこの方針を成立させたのは、大江広元・三善康信といった京下りの中下級貴族=実務官僚たちだった。
律令制から数百年をかけて少しずつ変質し、日本全国を覆うようになっていた「荘園公領制」という徴税システムは、複雑膨大なものであったから、それを御破算にしてゼロから新しい徴税システムを構築することなど、できっこなかった。少なくとも、そんな面倒なことをするよりも、パラサイトによって権力を確立するほうが、よっぽど現実的で手っ取り早かった。それに、徴税システムというものは、実務をこなす吏僚がいないと機能しないのである。(つづく)
 橘樹郡官衙遺跡に復元された倉庫。支配の基盤を為すのは徴税システムである
橘樹郡官衙遺跡に復元された倉庫。支配の基盤を為すのは徴税システムである
[参考図書]荘園公領制と鎌倉幕府の権力確立過程について詳しく知りたい方は拙著 『鎌倉草創-東国武士たちの革命戦争』(ワンパブリッシング)をご参照ください。