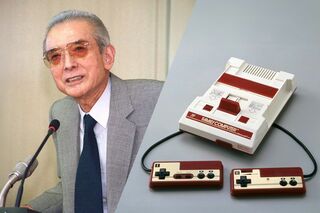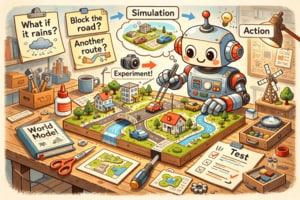なぜアクティビストの株主提案が通るようになったのか
2025年に設立150年を迎える名門企業・東芝は、昨年秋、上場廃止に追い込まれた。それもアクティビストの猛攻に耐えかねた結果、その対応に追われるより非上場企業
残り2955文字
2025年に設立150年を迎える名門企業・東芝は、昨年秋、上場廃止に追い込まれた。それもアクティビストの猛攻に耐えかねた結果、その対応に追われるより非上場企業
残り2955文字
ここからは、JBpress Premium 限定です。
カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら