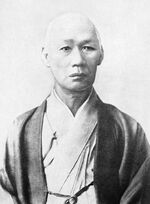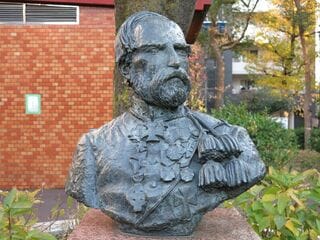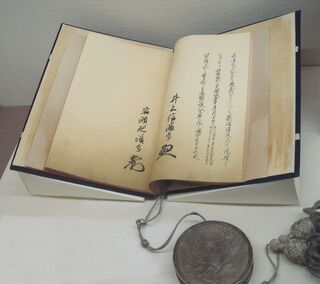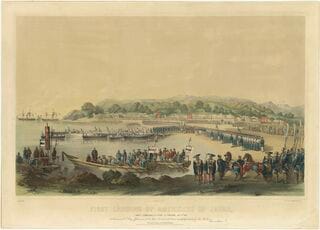薩摩藩主・島津斉彬、「民富めば君富む」をモットーに行われた民政と経済政策、ペリー来航を機とした海防強化の全貌
幕末維新史探訪2024(20)島津斉彬と幕末政治-日本近代化の基礎を築いた巨星④
町田 明広
歴史学者
2024.5.29(水)
ここからは、JBpress Premium 限定です。
カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら
連載の次の記事
島津斉彬による集成館事業の実態と、一橋派・南紀派に分かれた将軍継嗣問題との関わり