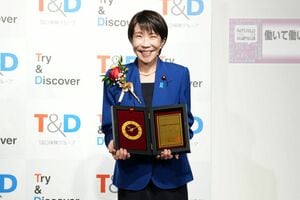見るだけではなく、保護者も参加する授業参観
佐藤:たとえ低学力であっても、自ら援助要請ができる子どもは、必ず低学力から抜け出すことができます。ところが、そうでない子どもは、必ず転落してしまう。そして、自身を転落させた、クラスメイトや教師、学校、ひいては社会を恨むようになってしまう。
だからこそ、協同的学びの中で、聞き合う関係を築いていくことが非常に大切なのです。
──保護者や地域の人が授業に参加する「学習参加」という取り組みにも言及されています。「学習参加」は「授業参観」と何が違うのでしょうか。
佐藤:学校は公共性を保つために、地域や社会に対して開かれた場所でなければならないということを、まずここで再認識していただければと思います。
研究授業によって、教師たちは同僚に対して教室の壁を開きます。しかし、保護者や地域の人に対しても、当然、教室を「開く」、学校を「開く」ということが重要です。
保護者に対しては、授業参観で教室を「開いて」いるのではないか、と皆さん思われるかもしれません。しかし現在の学校では、授業参観はほとんど機能していません。
小学校1年生の子どもを持つ親であれば、授業参観に参加するでしょう。しかし、小学校高学年、中学ともなると、授業参観に来る保護者の数は激減します。
日常の教室の状態について、ほとんどの保護者が無関心です。しかし、いい学校をつくっていくためには、保護者との協同は必要不可欠です。私は、学校改革に親が参画することは、親の責任であると考えています。
そこで、授業参観を観るだけのものから、参加するものにすることを、私は推奨しています。これが「学習参加」です。