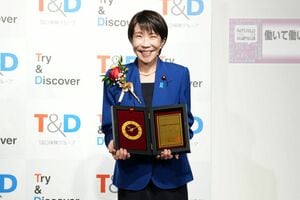学習参加に積極的な学校は保護者からのクレームも減る
佐藤:学習参加では、グループ学習に保護者に参加してもらいます。そして、学びの支援が可能であれば支援してもらう。支援が難しければ、子どもたちがどのように学んでいるかを観てもらう。子どもが小学校高学年になっても7~8割の保護者が学習参加に来てくれます。
最初の頃は、保護者は自分の子どものいるグループに参加しがちです。しかし、面白いことに、3回目、4回目の学習参加となると、保護者は自分の子どもがいないグループの活動に参加するようになります。
今まで自分の子どもにしか興味がなかった保護者が、よその子を支援しようとし始めるのです。教室が、パブリックな場になるのです。
さらに、学習参加を積極的に行っている学校では、保護者からの苦情がほとんどなくなるという報告も多数あります。自身も一緒に学校をつくっている保護者であれば、クレームを言う前に自身で学校を変えようという気持ちになるのだと思います。
──学びの共同体の学校改革の普及が困難な地域として、東京都、大阪府、京都府などの大都市と横浜市などの政令指定都市が上げられていました。 なぜ都市圏では学校改革を進めることが難しいのでしょうか。
佐藤:都市圏で学校改革が困難を極めるということは、世界共通の課題です。
なぜ都市圏で学校改革をすることが難しいのか。それは、資本主義の矛盾が顕著に表れるという都市圏の性質のためです。貧困問題や格差、多様な人のトラブル。こういったものはどうしても都市に集中しがちです。
しかし、その一方で都市部には多様な人が集まっている、というメリットがあることも確かです。一つの学校に多様な子どもがいるということはとてもプラスに働きます。
公教育の質の高さに関して、フィンランドやカナダ、オーストラリア、ニュージーランドなどがよく好事例として取り上げられます。これらの国の共通の特徴は、他民族国家、多言語国家であるという点です。
多様性を抱える国は、平等を意識せざるを得ません。したがって、それらの国は平等な教育を徹底しています。経済格差も、学力差もたくさんある子どもたちに、平等な教育を保証している。多様性がある方が、実は学校教育は高い効果を上げるのです。
日本で今問題となっているのは、都市圏での教育格差です。