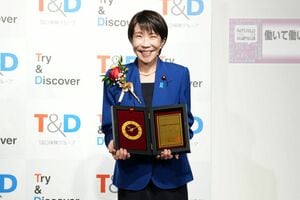「協力的学び」よりも大切な「協同的学び」
佐藤:協力(コオペレーション)は、お互いが足りないところを補い合うという考え方です。一方、協同(コラボレーション)は、多様な人々が交流し合って新しいものを創造する、という意味で捉えていただければと思います。
学びの共同体で必要となるのは、協同的学びです。複数の人間が相互に互いの違いから学び合って創造する。これこそ、今後求められる学びであり、現実的にも効果があるものだと信じています。
──なぜ、学びの共同体では、「協同的学び」が重要視されるのでしょうか。
佐藤:グループ学習における「協力的学び」と「協同的学び」の違いについて説明しましょう。
「協力的学び」は、子どもたちに「教え合いの関係」を築かせます。できる子ができない子に教える。実は、これは学びにおいては、あまり高い効果が得られないのです。
できる子ができない子に教えると、教えられた側は大抵の場合「分かった、ありがとう」と言います。しかし、実際に理解しているか、分かっているかというと、決してそうではない。
分からないの度合いや、何が分からないかということは、一人一人固有のものなのです。できる子が単一的に教えて解決できるようなことでは到底ありません。
自分の力で分からないことに立ち向かい、乗り越えていかなければ、真に「分かった」「理解できた」とは言えないのです。
分からない子が一生懸命考えているところに、既に分かっている子が口出しをすると、分からない子が自分の力で分からないことに立ち向かうことを妨げてしまいます。
一方、「協同的学び」では、子どもたちの間では「聴き合う関係」が構築されます。
グループ学習の中で、分からない子が必死で取り組んでいるときは、そっと見守る。これが重要です。分からない子が、自分から「分からないから教えて」と言い出すのを待つのです。専門用語では、これを「help seeking(援助要請)」と言います。
──書籍内では、「教え合う関係」は「待つ子どもを育ててしまう」と書かれていました。
佐藤:これは本当に深刻な問題です。
学力の低い子どもは、大きく分けて2種類います。分からないときに自ら「教えて」と言える子どもと、言えない子どもです。