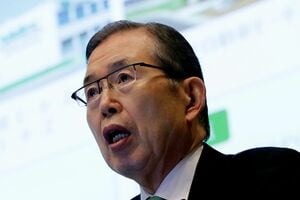先が見通せない有人ドローン「ブレイクスルー技術」の登場
困難なポイントはいくつもある。最大の難関は安全性だ。ドローンはヘリコプターと異なり、万が一動力が停止したときに風圧でローターを回しながら不時着するオートローテ
残り1980文字
困難なポイントはいくつもある。最大の難関は安全性だ。ドローンはヘリコプターと異なり、万が一動力が停止したときに風圧でローターを回しながら不時着するオートローテ
残り1980文字
ここからは、JBpress Premium 限定です。
カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら