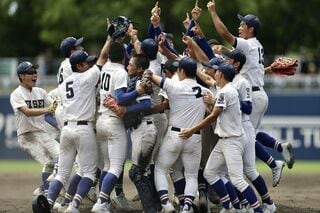不登校の実態は統計の3倍以上か
──何よりも子ども、そして親が問題を抱え込んでしまうのですね。
石井:不登校関連の公式データは、文科省が出しているものを参照するしかないのですが、原因だけでなく、不登校児童の数そのものも疑ってかからないといけません。文科省の不登校の定義は「年度内に30日以上欠席した子ども」となっています。
 「教師との関係」も不登校の大きな要因と見られているが、文科省の統計数字には構造的に現れにくい(写真:アフロ)
「教師との関係」も不登校の大きな要因と見られているが、文科省の統計数字には構造的に現れにくい(写真:アフロ)
しかし実態としては、学校には毎日通っていても、クラスに入るとおなかが痛くなるなどして保健室で日中を過ごす「保健室登校」や、「遅刻・早退を日常的にする」という子どもを合わせると、24.5万人ではとてもおさまりません。一説には、こうした「隠れ不登校」は、公式データの3倍以上いるのではないか、とも言われています。苦しんでいる子どもは皆さんの想像以上に多いのです。
──一般的に学校は不登校の子どもの心のケアを優先するよりも、「学校に復帰させる」ことを目的にしがちなのでしょうか。
石井:不登校になった子どもが元気になり、学校に戻って勉強すること自体は何も悪いことではありません。問題は「心の傷」を抱えたまま無理に学校に復帰させて状態が悪化することや、教師が家庭を訪問し「なんとか学校に連れ戻そう」とすることで、さらに子どもにプレッシャーをかけてしまうことにあります。学校側は「子どもを復学させること」がゴールとなりがちで、子どもの心の状態は二の次という対応になっている場合も珍しくありません。
学校側の事情もあります。人手不足などで教師の負担が増えており、生徒一人ひとりとしっかり向き合っている余裕がない、というケースが増えています。以前であれば解決できていた子ども同士のちょっとしたトラブルにも対処しきれなくなっているのです。
例えば、友達同士のけんかがあったとして、双方の言い分をしっかりと聞き、関係改善に向かわせようとすると手間がかかるので、つい、どちらか一方に謝らせることで仕事を早く終わらせようとしてしまう、ということもあります。あるいは、まだクラス内の力関係などに敏感ではない小学校低学年の子どもがいじめを先生に訴えたとき、「そんなのはいじめじゃないよ」と勝手に決めつけてしまう事例もあります。