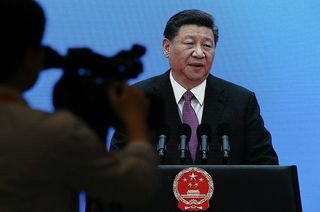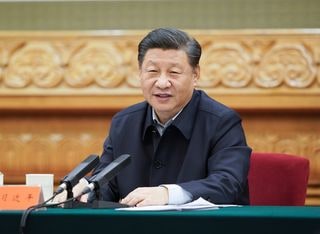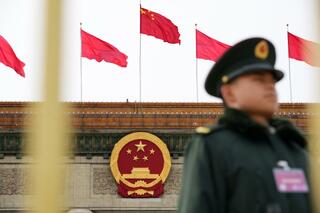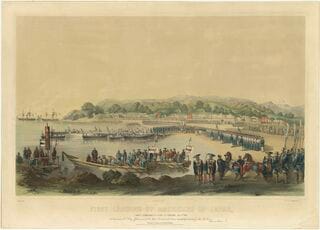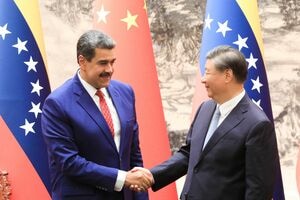一帯一路は、金融面でも問題を起こした。中国の政策銀行からの借入れは必ずしも安くはなく、中国開発銀行から借り入れた場合はその金利は4.5-6%であり、譲渡性が高いといわれる中国輸出入銀行から借りた場合であっても、2-3%である。これら金利は、世銀、ADBや先進国の開発援助機関からの借り入れた場合の1%前後と較べるとかなり高い。
このように中国からの借り入れ案件は、金額が大きいだけではなく、金利コストも嵩むので、途上国にのしかかる債務負担は重く、数年間の返済猶予期間が終わるや否や、半年毎の均等割賦返済に窮する途上国が多数出始めた。債務の弁済が滞った場合、その取り立ては厳しく、デフォルトに陥ると、中国国営企業はすぐさまプロジェクト資産の接収を開始したり、さらには債務の弁済に代わる地下資源の提供を途上国側に求めたりし、窮地に陥る国が見られた。
このような厳しい債権回収のやり方をみていて、中国は、“意図的にプロジェクトのサイズを膨らませ、貸せるだけ貸し込んでおいて、途上国を返済不能に追い込み、その上で、途上国の資産や地下資源を取り上げることを最初から目論んでいたのだ”とみる向きすら出てきた(いわゆる“債務の罠”)。
世界中に広がった「債務の罠」に対する警戒感
このように一帯一路はそれが開始されてから数年も経つと、それが内包していた問題が噴出し始め、これを見ていた現地政府は、プロジェクトの規模の縮小あるいは貸し付け条件の緩和を、さらには債務の棚上げを中国政府に求めた。しかし、中国政府は、最重要の国策機関である国営政策銀行が多額の不良債権を抱えるような事態は何としても避けたいと考え、途上国政府の要請には応じなかった。
こうした中国の債務救済に対する姿勢は、世銀、IMFが中心となって進めた、Debt Service Suspension Initiative (DSSI)においても表れた。DSSIは、COVID-19の蔓延に伴う債務の増大に直面する最貧途上国に対し、G20諸国が協調してその債務返済義務を一時的に猶予するとするものであり、2020年5月に始まり、その後半年毎に延伸され、2021年12月まで続いた。
その際に争点となったのは、債務の支払猶予の対象となる公的融資機関の範囲をどこまでとするかという議論であった。中国側は、この範囲を国家国際発展合作署と輸出入銀行に限定し、国営銀行である中国開発銀行は含めないとする立場をとった。世銀、IMFは、中国開発銀行の融資額が国家国際発展合作署や輸出入銀行のそれよりも遥かに大きいことから*5、DSSIの対象機関に中国開発銀行も含めるべきだと主張したが、中国政府は頑としてこれを受け付けなかったのだ。
*5 中国開発銀行の2013年から2018年までの年平均融資額は317億ドルで、輸出入銀行の2013年から2019年の年平均融資額は、217億ドルである。国家国際発展合作署については、それが提供する無利子融資の額は、これら国営銀行の融資額と比較すると遥かに少ない。