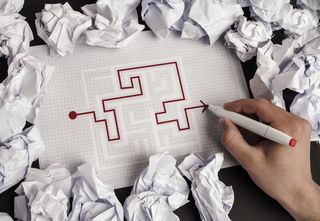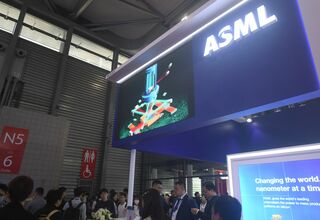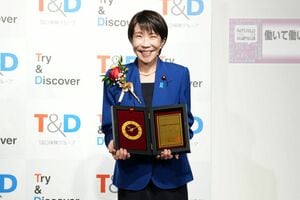ゲームは、油断していると達成できない、能動的に動かさないとゲームオーバーしてしまう、それでいて、少し努力すればなんとかゲームをクリアすることができる、そうした設計がうまくなされている。そういうゲームだと、のめりこんでしまう。ゲームのレベルデザインは、実に巧みな設計だ。能動性を発揮しなければクリアできない。でも少し背伸びすればクリアできる。ゲームオーバーしたとしても、「今度こそ、次のレベルまでクリアしたい」という能動性をうまく引き出している。
 ゲームのレベルデザインは実に巧妙
ゲームのレベルデザインは実に巧妙
何もかもお膳立てしたら、やる気を失ってしまう。能動的に関わることが必要なようにデザインされている必要がある。ただし少し背伸びすれば、次のステージに進めるようにデザインされている必要がある。何もかもお膳立てするのではなく、「能動的に働きかけ、今の能力より少し背伸びしないと達成できない」ようにデザインされていると、ゲーム感覚でのめりこむようになる。
「少しの背伸びでクリアできるレベル」が肝心
ロバート・オウエンという人は、こうした設計が巧みだったらしい。自伝によると、それぞれの職人の持ち場に、色札をぶら下げていたのだという。仕事の丁寧さ、速さごとに色で分類した。すると、自分も次のステージの色札になりたくて、腕を競うようになった。一種のゲームにしたのだ。
現代でも、次のような面白い事例がある。レジ打ちの技術が人によってまちまちだったスーパー。それまでは、空いているところにめいめいにレジ打ちに入る仕組みにしていたのだけれど、レジ打ちの一番上手な人を最前列にし、その次にうまい人は一番うまい人の後姿を見る位置に、3番目の人は・・・と、レジ打ちのうまい順に並べたところ、「技を見て盗む」ような感覚で、全体にレジ打ちの技能が向上したという。
ここで注意したいのは、「競争」とは少し違う、ということだ。レジ打ちがうますぎる人の横に、そうでもない人を配置しても、学ぶ意欲は発生しにくい。レベルが違いすぎて諦めてしまうからだ。けれど、少し背伸びすれば自分にもそれができそう、と思うと、やってみたくなる。人間には、「できない」を「できる」に変えられると、快感を覚える仕組みがあるようだ。「できない」を「できる」に変えるには、今の実力で、少し背伸びすれば達成できるかも、というレベルデザインが重要。テレビゲームのレベルデザインの考え方が、とても有効だ。
能動的に動かないことには、事態は変わらない、という状況を作ること。少し背伸びしなければ、達成できない状況にしておくこと。けれど、少し背伸びさえすれば、「できない」を「できる」に変える快感を覚えられる、レベルデザインにしておくこと。
そうした設計をすると、テレビゲームに何時間ものめりこむ子どものように、のめりこむ。そういう意味では、学ぶことも働くことも、ゲームとさほど変わらない。
人間には、もともと成長意欲が備わっている。しかし、その意欲をそぐ障害がいくつもあり、「とても今の自分ではやれそうにない」と、すっかり諦めてしまうことが多い。あるいは、お膳立てしすぎて、能動的に解決する余地さえも奪われて、面白みがなかったりする。どちらも、両極端だ。
能動的にならなければ、待っていても何も起きない。能動的に動かなければ解決しない。ただし、能動的に動いて、少し背伸びすれば解決できるかも。そうした条件を設定すると、ゲームと同じようにのめりこむ。意欲は、自然に湧いてくる。
ゲームにのめりこんだ子どもは、例外なくそのゲームの巧者となる。一面もクリアできなかった最初の頃からは、想像もできないほどのワザを身につけているだろう。
仕事も学びも、そんな風に成長を促す仕組みがほしいものだ。もっともっと、ゲームのレベルデザインの巧みさから、学んだ方がよいように思う。