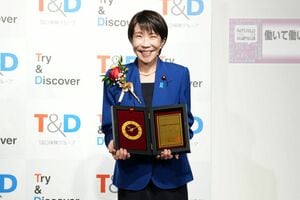大学と文科省の関係の行く末は・・・。
大学と文科省の関係の行く末は・・・。
前回の記事(http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/53915)では、「2018年問題」*1への文科省の対応の目新しさは、結局のところ、大学間の連携と統合を円滑に進めるための枠組みづくり(国立大学法人のアンブレラ方式、私立大学の学部単位の事業譲渡、大学間での、あるいは地域や産業界を巻き込んだ連携を推進するための組織の設置)という点に落ち着いたことを見た。
今回は、高等教育政策として、こうした対応をどう評価したらよいのかについて考えてみたい。
*1:2018年を境として18歳人口が減少傾向に転じ、それが、各大学にとって、入学者の確保を困難にし、ひいては大学そのものの存続を危機に陥れかねないという「問題」。
「将来像の提示」と「誘導」という基本路線
ただし、本題(中央教育審議会(中教審)の大学分科会「将来構想部会」の「中間まとめ」に盛り込まれた今回の対応についての検討)に入る前に、視点をより広く持っておきたい。というのも、いよいよ「2018年問題」が到来した現段階での文科省の対応は、実際には、2000年代に入って以降の高等教育政策の基本路線によって、大きく制約されていたはずだからである。
では、2000年代以降の高等教育政策の基本路線とは、何だったのか。それは、設置基準の「大綱化」を標榜した1991年の大学設置基準改訂以降、規制緩和という形で徐々に進みつつあったものであるが、それを象徴的な表現で、高等教育政策の転換として示したのは、前回の記事でも触れた2005年の中教審答申「我が国の高等教育の将来像」であった。いわく、今後の高等教育政策は、従来のように「高等教育計画の策定」や「各種規制」に重きを置くのではなく、「将来像の提示」と政策的な「誘導」を主たる任務とするのだ、と。
結局、その後は、どう動いたのか。時代は、新自由主義に基づく社会構造改革が強力に推進され、規制緩和によって競争原理を働かせることこそが、活力や成長を生むのだといった社会思潮の全盛期であった。文科省の政策も、大学や学部の設置認可に関しては大幅な規制緩和を繰り返したため、次々と新規の大学・学部が設置され、大学は量的な拡大を遂げていった。いわゆる「団塊ジュニア世代」の通過以降、18歳人口はすでに減少期に入っており、将来的には落ち込むことが誰の目にも明らかだったはずなのに、である。