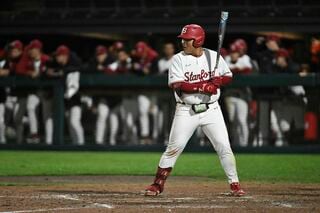光冨:肺癌学会としても、長谷川さんという患者さんへの窓口ができたことは非常にありがたいです。患者さんの声を聞くにしても、以前は誰に声をかけたらいいか分かりませんでしたから。様々な点で、非常にいいパートナーとして認識しています。
「コラボレーションによって成果を出したことの意味は大きい」
――近年、肺がん医療は大きく進歩しています。長く生きられる患者さんが増えたことで、「医療の在り方」や、「医師と患者のコミュニケーション」も変わってきているのではないでしょうか。
光冨:だいぶ昔の話になりますが、私が医師になってすぐのころは、「患者さんは何も知らなくてもいい」という風潮が日本にありました。学生時代は「がんの告知なんてするな」と言われていましたし。それがだんだんと本人に告知をするようになり、患者さんの希望とか、生き方を聞きながら治療をしていくようになりました。
長谷川:近年は、肺がん患者の心の有り方が激変しているのではないかと思います。以前は「どう生きていきたのか」という問いに悩むことすらできませんでしたが、今は、治療ひとつに対しても希望を言えるようになっています。「脱毛はいや」とか、そういった希望でも医師が一緒に考えてくれる、というふうに変わってきました。
しかし、年単位で延命できるようになった今では、「この先、どうやって生きていくんだろう」というような思いを抱くこともあります。そこは誰も教えてくれないので、医師とのコミュニケーションの必要度が上がっていると思います。

光冨:以前は治療法もなかったですし、「がんの宣告」が、即、「死の宣告」といったようなところがあり、何かを選ぶ余地もありませんでした。医学の進歩によって治療の選択肢が増えたことで、いろいろと別の悩みも増えているかもしれません。そのため、ますますコミュケーションが重要になっていますね。
――肺癌学会と患者連絡会が協働し始めたことでの変化や成功事例を教えてください。
光冨:我々は肺がんの研究をしているけれど、その多くは肺がんの経験をしたことがありません。ですので、やはり病気になっている方がどのように思うかを聞きながら理想の医療を作っていくというのは非常に重要な活動だと思います。患者連絡会とつながり、患者さん側の意見を取り入れられているおかげで、新薬の承認などを規制当局への働きかける際にも、説得力のあるお話ができていると思っています。